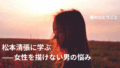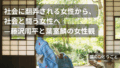AppleからOS26シリーズがリリースされて一週間が経った。ご多分に漏れず、さっそくインストールして試してみたので、その使用感を記しておく。
私が愛用しているiPadはiPad miniだ。常に手元に置いており、利用頻度はiPhoneより高い。
iPad OS26に私が最も期待していたのは、iPad miniで使えるようになった「ステージマネージャ機能」だ。特に外部ディスプレイに接続したときに、外部ディスプレイ側で使えるのではないか、ということだった。
これができると、iPad miniはiPad Pro並の機能と使用感を得ることになる。iPad mini自体のディスプレイは狭いが、広い外部ディスプレイの画面でアプリが使えるようになるというのは大きなメリットだろう。
この点について結論から言うと、残念ながら、期待は大きく外れた。iPad miniに外部ディスプレイを接続すると、ステージマネージャが無効になってしまう。
これは、iPad miniでは外部ディスプレイにおけるステージマネージャはサポートされていないと言うよりも、そもそもiPad miniは外部ディスプレイ接続についてはミラーリングしかサポートされていないと言うべきだろう。
ミラーリングされた画面もiPad miniの画面がそのまま拡大され、解像度が変わるわけではないので、使い勝手は良くない。iPad miniによる外部ディスプレイ前提の運用は諦めた方が良い。
しかし、ステージマネージャについては別の気付きがあった。
ステージマネージャは複数のグループにウインドウを整理することができる。これがiPad miniの狭い画面で、多くのアプリを切り替えて使う上で非常に有用であることが分かった。
この話をする前に、私がどういう用途でiPad miniを使っているか、整理しておいた方が良いだろう。
まず、執筆時の辞書。これは物書堂さんのアプリで日本国語大辞典、大辞林、新明解国語辞典、日本語シソーラス、ウィズダム英和辞書を使っている。
次にメモ。小説やエッセイのアイディアメモにはDraftsを使っている。Draftsは、iPad miniを手に取って起動するとすぐに入力状態になっているので、メモを取ることにストレスがない。
スケジュールはプライベートの管理には純正のカレンダーを使っている。IT関係の仕事では、会社がGoogleを使っている関係でGoogleカレンダーだ。予定が多すぎて混乱するので使い分けている。
コミュニケーションツールは、純正のメッセージとFaceTime、LINE、ときどきDiscordを使う。
最後に、読書。私は基本的に漫画はhonto、それ以外の書籍はKindleで管理している。これは、単に1つのサービスで全てを管理すると読みたい本を探すときに苦労するからだ。
最近老眼が進み、電子書籍率が上がっている。文字の大きさを変えられる電子書籍は、今の私にとっては必須と言える。
ちなみに、私は昔の大御所の全集を古本で買って読む。藤沢周平、吉村昭、池波正太郎など。全集は字が小さいので、正直目にきつい。こういった全集は、是非電子書籍化を検討してほしい。
このように、複数の用途で多くのアプリを使っている場合、ステージマネージャの「複数のグループにウインドウ(アプリ)を整理する」機能は、使い勝手と生産性向上に寄与する。
例えば、Draftsを開いた状態で、ObsidianをドックからDrafts上にドラッグ&ドロップするとDraftsとObsidianがグループになる。そうすると、他のアプリを起動したときに、このグループ化されたアプリは1つのアプリ群として扱われるので、下から上にスワイプしたときの表示やステージマネージャの左側のアプリ一覧で1つのアプリ群として表示される。
執筆に使うアプリとコミュニケーションに使うアプリをそれぞれグループ化しておくと利便性は上がるだろう。私の場合、下記のグループを作った。
– 執筆グループ:Drafts、Obsidian、辞書、Claude
– ブロググループ:WordPress、note、Canva
– コミュニケーショングループ:メール、メッセージ、LINE
– スケジュールグループ:カレンダー、リマインダー
– 読書グループ:Kindle、honto
一週間使ってみて実感したのは、グループ化によるアプリ切り替えの速さだ。アプリをグループ化する前は、下から上にスワイプすることで表示されるアプリの一覧から目的となるアプリを見つけていた。目的のアプリを探すのは一苦労だった。グループ化してからは下から上にスワイプし、画面の途中で止めることでグループ内のアプリが一覧されるので、目的のアプリが非常に見つけやすい。
例えば、DraftsのあるメモをObsidianに送ったあと、すっとObsidianに切り替えて執筆に着手できる。
辞書を使うときも同様だ。言葉を調べたいと思いついたとき、今まではアプリを切り替えている間にその言葉を調べたいと思った「想い」が覚めてしまうことがあった。これは実際に書いていないと分からないかもしれないが、ちょっとした動作や一手間で書く熱意やアイデアは吹き飛んでしまう。グループ化することで辞書は即時に見つかるので、そういった感覚はこの一週間無くなった。
また、グループ全体を一つの「作業空間」として扱え、1日の行動に合わせて切り替えられるのも良い。
例えば、朝の散歩後、私はまずスケジュールグループで一日の予定を確認し、次にコミュニケーショングループで返信を済ませ、最後に執筆グループに切り替える。Draftsでアイデアを整理したあと、本格的な執筆に入る。
この「モード切替」が明確になったことで、集中力が保ちやすくなった。
一方で、身体がステージマネージャの動作を覚えるまでは少し逆の煩雑さはあったのは確かだ。ステージマネージャのリストの出し方、グループ内のアプリの切り替え方、すべて指で操作するのがiPadなので、設定を変えてからの数日は違和感があった。
しかし、今では身体がこれらのジェスチャーを覚えてしまったので、全く問題ない。
これらのアプリを常時起動していると動作が遅くなるかと最初は心配したが、今のところそういったことも無い。
もっとも、グループ化が必要ないと言うことであれば、従来からある「フルスクリーンアプリ」で十分だ。使うアプリが少ない人は、これだけでも十分便利だと思う。
iPad miniの良さは、使い回しの良さ、速さにある。それを考えたとき、今回のiPad OS26はそれほど大きなインパクトがあるものではない。ただ、小さな画面で多くのアプリを効率的に管理したいのであれば、「ステージマネージャ」は十分に選択肢に値する。
iPad miniに限った話ではないが、やはり自分のユースケースをしっかり理解、定義してから新しい機能は使っていくべきだろう。