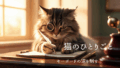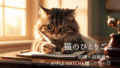AIを活用してどのように文章が書けるのか、いろいろと試行錯誤してみました。最初に断っておきますが、わたしは文章を書くこと自体が好きで文章を書いています。ですので、一番楽しい「文章を書くこと」をAIに明け渡すつもりはありません。ここでは、その楽しい文章を書くことを毎日続けるために、AIになにを協力してもらうのか、を主に書いていきたいと思います。
まず、どんな文章を書くかアイデア出しをします。アイデア出しというのは、楽しくもあり、難しくもあるプロセスです。一般的に、ひとりで考えるよりも他の人間と会話しながら考える方がアイデアも湧きやすいです。ですので、AIを壁打ちに協力してもらいます。
壁打ちというのは、AIとの雑談です。最近聞いた話や、ニュース、なんでもいいですが、AIと会話をしてみましょう。分からないことは聞き、AIの回答が間違っていると思えば指摘する。それを繰り返していると、アイデアのネタが生まれることがよくあります。
わたしの場合、エッセイの壁打ちはChatGPTを使うことが多いです。これは、Apple IntelligenceがChatGPTと連携しているからです。わたしはエッセイは純正メモアプリで作成しているので、Apple Intelligenceの方がAIへのアクセスが容易です。今後連携するAIが増えてくれば、他のAIにするかもしれません。
小説を書く場合の壁打ちはClaudeを使います。小説を書く場合はWordやテキストエディタを使うことが多く、特にApple Intelligence経由AIを使う必要がありません。また、Claudeを使う理由は、単に相性というか、わたしの好みです。なんとなくClaudeとの文章のやり取りの方がストレスが少なく、安心感があるのです。
ネタができたら、いちから文章を書き始めます。ここはもっとも楽しいプロセスなので、AIに手伝ってもらうことはありません。
ただ、文章を書いていると、時々分からないことや調べたいことが出てきます。そのときはAIに調べてもらいます。わたしが調査のために使っているAIはChatGPTです。調べてもらったことは、念のためにソースを確認して自分の目で裏取りしています。調査のクロスチェックとしてClaudeを使うこともあります。
記事ができあがったら、AIに校正してもらいます。校正はClaudeにお願いしています。Claudeは誤字脱字だけでなく、文章の構成や情報の確かさについてもチェックしてくれるので、非常に信頼性が高いです。ただ、明らかにおかしいと思う点や、わたしが腹落ちしない内容については、必ずツッコんで確認するようにしています。
最後は、自分の目で校正です。AIを使っていなかったときは、最低でも3回は校正をしていました。多いときは5回、小説などの場合はもっとしていたと思います。しかし、AIを使うようになってからは1回で済むようになっています。文章が2,000文字程度の短いものですとあまり恩恵はありませんが、文章が長くなってくると馬鹿にはならない時間の節約になります。
このようにAIを活用していて感じることは、AIの時代になると本当に必要な能力は、AIとのコミュニケーション能力だということです。AIの回答の質は、プロンプトに大きく左右されます。プロンプトの質が高いと、AIから返ってくる回答の質も高いです。ですので、AIを活用するためには、的確なプロンプトを作成する能力、つまり日本語で的確に伝える力が不可欠です。
的確なプロンプトの特徴として、AIに役割を与える(「プロの編集者として」「プロの脚本家として」など)ことで、より専門的な応答を引き出している点が挙げられます。また、具体的な指示と制約を設けることで、AIが創出する文章の質と方向性をコントロールしています。これらは、日本語の能力が高くないとできないことです。
また、AIはネットやさまざまなソースから情報を収集して、整理し、まとめてくれます。そのアウトプットは整理されているとはいえ、膨大なものになります。それを読みこなすのは決して簡単なことではありません。AIが生成した文章を正しく評価し、適切に校正する力、すなわち文章を深く読む力が求められます。
結局のところ、今後AIの進化に伴い、それが身近になっていくなかで、人間に求められるのは「文章力」、つまり国語力です。AIはあくまで補助的なツールであり、最終的な質を決定するのは私たち自身の言語能力です。AIから提示された情報を読んで、判断し、決断し、その結果に責任を負うのは人間です。いままで以上に人間側の国語力が大事な時代になってきているのではないでしょうか。
子供たちの国語力の低下が問題になってから久しいです。以前、試験問題の日本語が理解できなくて、回答ができないといった子供たちが増えているというニュースがありました。子供たちだけでなく、大人も、SNS時代の影響で、短い文章、短い動画に慣れてしまい、「タイパ」ばかりが優先されて、ものごとを理解する力、表現する力が落ちていると言われています。
しかしどう考えても、教育の最優先課題は国語ではないでしょうか。英語も、数学も理科も、誤解を恐れずに言えば、AIが全部やってくれます。正しく指示すれば計算してくれるし、結果も返してくれます。しかし、正しく指示できなければ正しい結果は返ってきません。また、AIが返してきた内容が正しいかどうか、国語力がないと判断できません。AIを使いこなせる人間は国語力のある人間であり、今後の時代を生き残っていける人間は国語力のある人間になるのかもしれません。
AI時代は、文章作成はAIがやってくれるからといって、文章力が必要ではなくなる時代ではないのです。AIに思うとおりのアウトプットを出してもらうためにも、またAIが正しいアウトプットを出してくれたかどうかをチェックするためにも、いままで以上に文章力が必要になってくる時代なのです。そしてそれが、もしかしたら、将来シンギュラリティポイントを超えたあと、人間がAIと共存するひとつの鍵になるかもしれません。