昨日、毎週行っている同僚との 1 on 1 のミーティングで、相談事を受けました。どうやら同僚は、会社を辞めたいと考えているようです。わたしも2回この会社を辞めて2回入り直した人間ですし、人生を振り返っても4回は転職をしているので、少しはアドバイスできることもあるのかなと話を聞きました。
同僚いわく、最近の会社の方針に疑問を感じるとのこと。その方針とは、極端に言えば「AIにこそ価値がある。そのAIを売って稼ごう」という考え方です。同僚はその方針に違和感を感じると言うのです。
同僚の主な疑問は2つです。第一に、果たしてAI自体が会社の価値となり得るのかという疑問。第二に、自分たちが十分に活用できていないAIソリューションを顧客に提案することへの倫理的な懸念です。
この疑問はわたしも常々感じていました。第二の疑問は、会社の販売戦略の話になり、AIとは直接関係がないので、今回のトピックからは除外します。ここでは、第一の疑問について考えてみたいと思います。
前もどこかで書いた記憶があるのですが、AIそのものに価値があるのか? という質問は、実はもはや愚問と言って良いと思います。あります。間違いなく。でも、それは「AI」の価値であって、それを使う「企業」の価値ではありません。ここをはき違えている人が意外に多いように思います。
分かりやすい例で言うと、水や電気には価値がありますよね。それがないと人間は生きていけませんし、文明的な生活を送ることができません。しかし、水を飲む、電気を使う「人間」にどういう価値があるかは、水や電気とは関係ありません。
AIはここで言う水や電気と同じであるとわたしは考えています。遠くない未来に、あって当たり前の公共財的な存在になることは間違いありません。AIを使えること、AIが機能として盛り込まれていることにはもう価値は無くなります。「AIにこそ価値がある。そのAIを売って稼ごう」という言葉は、「水や電気にこそ価値がある。その水や電気を売って稼ごう」と言っているに等しいのです。
価値とは、希少であればあるほど高くなります。AI自体はもはや希少ではありません。既にだれもが、どこでも使えるものになりましたし、今後さらにそれが進んでいきます。AIを使うかどうかは最早議論になりません。使うことがベースラインになります。そこが出発点であって、到達点ではないのです。
わたしは、最近AIと一緒に執筆活動をしています。年齢から来る集中力の低下、持続力の低下、記憶力の低下、これらをリカバリしてサポートしてくれる存在だからです。でも、それだけでは何も生まれていません。AIのリカバリを踏まえて、わたし自身の能力をフル回転させて、わたしの創作物、文章、物語を書かなければなりません。価値があるかどうか、問われる対象はAIではなく、わたしの成果物です。
わたしの周りで仕事でAIを使っている人たちの中には、このベースラインから抜け出られていない人が多いように見受けられます。過渡期的なものなのかもしれませんが、AIを使うことで満足してしまって、頭を使ってその先を産み出すことを忘れているのです。これでは、その人の価値は出ませんし、会社の価値にはなりません。企業価値というのは、その企業でしか実現できない、希少な製品、サービスからしか生まれません。
企業がAI時代に真の競争優位を築くためには、AIはもちろん最低限の要素ですが、それだけではダメです。AIを人間と同じ従業員としていかに活用していくか。ヒト、モノ、カネの企業の三要素のひとつとして管理できるかどうかがポイントになります。
AIはもはやあって当たり前のものです。活用することが息を吸うのと同じくらい当たり前になります。同僚が、漠然と感じている違和感、不安感の正体は、わたしはここにあるのだと思っています。AIを価値として捉える思考から脱却し、AIを活用した真の価値創造に向けて、一刻も早くスタートダッシュを切ることが、個人としても企業としても求められているのです。
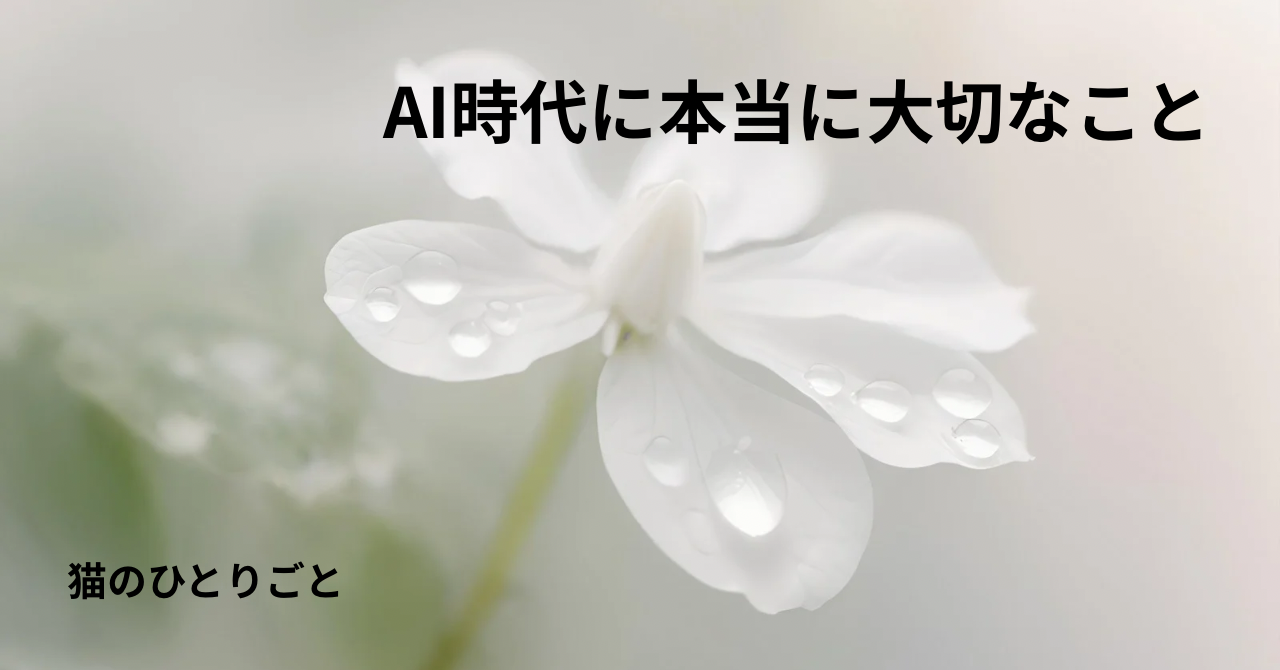
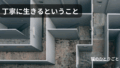
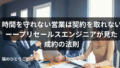
コメント