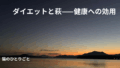AIは創造の敵か、味方か。
タイトル通りである。先に私の答えを書いておこう。
味方である。が、それは使う人間次第だ。
私の本業であるITの仕事を例にとろう。2つのシーンを紹介するが、これらは実際にあったことだ。
1つは、営業と一緒に提案の資料を作ったときの話だ。
ある営業がお客様がおかれているマーケットと業界の状況、お客様からのヒアリングの内容を踏まえて、提案書を作ってきた。上司に見せる前にレビューしてほしいということだった。
読んでみて驚いた。テキストだらけなのである。スライドの頭から終わりまで、文字がびっしりと詰まっている。
「なんですか、これは」と彼に問うと、「Geminiが作ってくれたんです。すごいですよね。数分で出来るんです」と答えが返ってきた。
中身を読むと、なるほど間違ったことは書いていないし、なかなか良い分析になっている。しかし、だ。
「これ、ここの表現、どういう意味なんですか?」と聞いてみたら、答えられない。
そう、彼はAIの回答をそのままコピーしただけなので、”彼自身は中身を理解していない”のだ。
最近こういうシーンが多い。AIを使うようになったのはいいのだが、自分の頭を通さないでそのまま使う人が結構いるのだ。
だいたい、お客様の提案資料で、中身がどんなに良くて正しいことを書いていても、こんなテキストだらけの資料、誰も読まない。ただでさえ、日本語読解力が落ちている昨今である。文章を読み慣れている私でさえ息切れするくらいのテキストの量だった。
もう1つの例を挙げよう。これは、あるデモンストレーション(デモ)を作っている際のできごとだ。
私は基本的にできるだけ標準機能を使ってデモを構築することにしている。カスタマイズをするとお客様の要件が変わったときにデモを修正するのが大変だし、今の仕事のやり方や運用を変えて、いかに標準で要件を実現するのかを考えることがアプリベンダープリセールスエンジニアの仕事の醍醐味だと思っている。
しかし、どうしてもある開発言語で実装しなければならないシーンが出てきた。しかもデモまでの日にちがない。
私はさっそく、Geminiにコードを書いてもらった。こういうときこそのAIだろう。
あっという間にコメント付きのコードが出力された。しかしそれを見て私は考え込んでしまった。コードが理解できないのだ。
頭からソースを読んでいくと、もちろん書いてある内容は分かる。しかし、なぜそのコードがそういう結果を出せるのかが分からなかった。実行すると、確かに正しい結果が出る。何故だ。
種明かしをすると、そのソースコードは、私の知らないアルゴリズムを使って書かれていたのである。
そこからGeminiとの会話が始まる。このアルゴリズムはどういうものなのか説明してくれ。
Geminiは丁寧に教えてくれた。目から鱗が落ちた。昔読んだプログラミングの本を引っ張り出してきて、Geminiの回答の裏を取っていく。
アルゴリズムとその周辺知識を理解した私は、自信を持ってデモをお客様に披露することになった。
この2つの例は、AIと人間の関係を非常に良く表すものだと思う。かたや、その出力を鵜呑みにしてそのまま使う。かたやその出力を疑い、あるいは自分の知識を疑い、調べ、自分の頭で考え、理解する。
この違いがお分かりだろうか?
創作におけるAIの活用も全く同じだと思う。こういう物語を書きたいとプロンプトに書いて、AIに文章を書いてもらう。良いだろう。別に私は否定しない。だが、それを”そのまま”使うことには抵抗がある。少なくとも私はしない。理由は簡単だ。私は、書くことが好きなのだ。なんで好きなことを放棄してAIにやらせるのか、私には理解できない。
もう1つの理由は、AIが書いたことは、AIが学習してきたことを元にしている。つまり、”過去に誰かが書いたことのある”ものを学習してアウトプットしている可能性がある。これをそのまま使うことは、著作権上問題があるかも知れない。
もちろん、我々の創作物は多かれ少なかれ、過去に先人たちが書いてきたテキストの上にあって、何らかの影響を受けているし、むしろそれに憧れて近付こうとする。しかし、AIのアウトプットを使うこととそれとは本質が異なるのだ。
AIは基本的にプロンプトの内容とグラウンディング(AIに参照させる情報の提供)される情報によってアウトプットを出す。いまはプロンプトをどう書くか、どういうデータをどうやってグラウンディングするのかに焦点が当たりすぎている。
私は、AIのアウトプットをどう評価するか、それを人間の頭で考え、自分の脳細胞というフィルターを通してどのように使っていくのかの方がよほど重要だと思うのだ。
その意味で、AIはエージェントの時代を迎え、MCP(AI同士やAIとアプリの連携技術)を中心として”AIの後処理”が注目されてきているのは、至極当然のことと言える。
最初の問いに帰ろう。AIは創造の敵か、味方か。
AIに対するインプットのみに意を用いる者にとっては、AIは敵になり得る。そのアウトプットが人類のためになる保証がないからだ。AIからのアウトプットを大事にしてこだわる者にとっては、AIは味方になる。その人間の能力を補完し、生産性を上げ、創造性を高めてくれるだろう。
人類がこの2種類に分けられるのだとしたら、私は後者のカテゴリでありたい。