昨日、とあるお客様先を訪問し、AI導入に関するワークショップを行いました。
お客様の業務をヒアリングし、「どの業務の、どの作業にAIを使うとよいか」をみんなで議論し、ユースケースを明らかにするのが目的です。もちろん、その先に導入を見据えてROI(投資対効果)を検討することも視野に入っています。
目的こそ「ユースケースとROIを明らかにする」ことでしたが、現場の空気は驚くほど自然でした。
「AI? それって何? 役に立つの?」というような拒否反応はなく、「ああ、あれね」とでも言うような、新しい同僚を迎えるような雰囲気。
拍子抜けするほど、違和感がなかったのです。
「これ、AIにやってもらえるとありがたいよね」
「定型作業はもう任せちゃいたい」
そんな会話が笑顔まじりに交わされ、場はごく普通のミーティングのように進んでいきました。ときにはジョークも混じり、AIに名前や顔のイラストを描いてみたり。ワークショップというより、雑談に近い空気感だったかもしれません。
ただ、わたしはこの「違和感のなさ」に、むしろ強い違和感を覚えました。
なぜこれほど自然に受け入れられたのでしょうか。改めて振り返ってみると、お客様の反応には明らかな特徴がありました。
過去にクラウドやSNSを企業に提案したときのことを思い出してみると、当時はもっと慎重でした。「セキュリティは大丈夫なのか」「本当に効果があるのか」「従来のやり方でも十分ではないか」といった議論が必ず起こったものです。
しかし、昨日のワークショップでは、そうした根本的な疑問はほとんど出ませんでした。むしろ、「どう使うか」が前提となって話が進んでいく。まるでAIがすでに身近な存在として認識されているかのようでした。
もしかすると、AIはすでに「特別な技術」ではなくなっているのではないか——そんな仮説が頭をよぎりました。
お客様のほうがわたしたちよりずっと先を進んでいて、わたしたちが置いて行かれているのではないか。AIの技術を紹介し、活用の可能性を語り、ユースケースを探る——そうした一連の流れそのものが、すでに「不要になりつつある」、あるいは「ナンセンスではないか」とさえ感じたのです。
この仮説が正しいとすれば、これまで当たり前だった「ユースケースやROIの特定」というプロセス自体を問い直す必要があります。
思えば、わたしたちはいまや「Excel導入ワークショップ」や「メール活用講座」などを開くことはありません。それらはすでにツールというより、「前提」になっているのです。
しかし、それなのに「AIを使ってどう差別化するか」「どれほどのROIがあるか」といった議論が、いまだに社内では根強く残っています。けれども、本当にそれがどれほど重要なのでしょうか?
AIで「差別化」を図ろうとする発想自体が、もしかすると時代遅れなのかもしれません。本質的な差別化は、その企業自身が持つ価値によって決まるもの。AIはそれを加速する、当たり前のツールにすぎないのです。
AIは「これから使うもの」ではなく、「すでにそこにあるもの」になりつつあるのではないか——わたしはそう考えるに至りました。
つまり、AIは空気になる。
電気や水道のように、わたしたちが日々使っていることさえ意識しなくなる、そんな存在感へと近づいているのだと。
つまり、AIを使うか使わないかではなく、AIを使って何を成し遂げるかが、あらためて問われているのです。
営業さんが運転してくれる帰りの車のなかで、ふと考えました。
「ワークショップがいらなくなる日」は、決してAIが使われなくなる日でも、人間にとって不要になる日でもない。
むしろ、それはAIが人間の暮らしやビジネスにとって「当たり前のもの」として根付いた日なのではないか。
だからこそ、わたしたちがお客様に次に問うべきなのは、こういう問いではないでしょうか。
「あなたのビジネスは、あなたの顧客に対して、AIとともに、どんな世界を作ろうとしているのですか?」
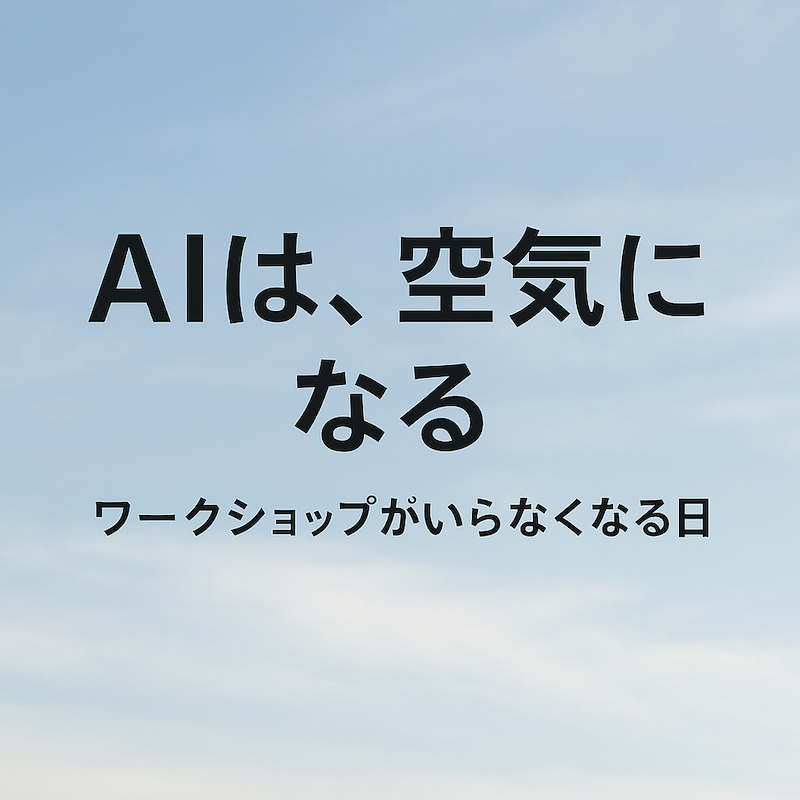
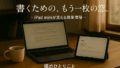
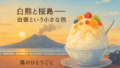
コメント