「男はつらいよ」という映画のシリーズを、最近の若い方はご存じないかもしれません。わたしのような昭和世代にとっては、ほぼリアルタイムで公開されていた劇場映画で、だいたいお盆とお正月の時期に年2本上映されていました。
個人的には劇場で観た記憶はあまりなくて、テレビの映画劇場の再放送などで何度か観た程度です。大学のとき映画を観るお金もなくて、使い放題だった大学の視聴覚室にあるシリーズを全部観た記憶があります(いま考えてみると、あれもテレビの録画だったのではないかなと思います)。
前もどこかで書きましたが、当時のわたしは大分から東京に出てきて里心がついている時期だったので、「男はつらいよ」シリーズは心の癒やしになっていました。このシリーズは主人公であるテキ屋の寅さんの郷里である東京下町葛飾柴又が舞台になっています。しかし、寅さんは流浪のひと。日本中を旅してまわりますので、その行く先々の風情が、郷里を思い起こさせるのです。
そんな「男はつらいよ」シリーズを観なくなったのは、いつのころからだったか……。正確な時期は覚えていませんが、どこかのタイミングで寅さんを観ているのがしんどくなって、彼が演じるドタバタ劇も、人情劇もなんとなく肌があわなくなって、観なくなったような気がします。今回、この本を読んで、その理由が分かったような気がしました。
約800ページ、価格にして1万円を超える大著です。久し振りにこんなに分厚い本(しかも紙の本!)を読みました。今年1月17日に購入したので、約1か月で読み終えたということになります。毎朝のウォーキングしながらの読書は司馬遼太郎なので、それ以外の空いた時間を見つけながら読んだにしてはよいペースかなと思います。
この本は、「男はつらいよ」で有名な山田洋次監督の評伝です。しかも、日本人ではなく、フランス人が書いたもので、わたしが読んだのはその翻訳です。元々の文章がよいのか、翻訳が巧みなのか、翻訳特有の違和感は全くなく、日本語がオリジナルであるかのような読後感でした。
山田監督の人生を子供のころから振り返って、つい最近まで、それこそ去年2024年の状況まで詳細に記述してあります。山田監督の評伝なので当たり前なのですが、彼の人生をこの本で追体験ができます。わたしはそれだけでなく、あたかも戦後日本の歴史を見ているような、読まされているような気分になりました。
この本の主題は、おそらく、山田監督の活動や制作した映画を通して、戦後日本人の社会、文化、精神のあり方がどのように変遷していったのか、それに対して監督がどういう態度を示し、なにを日本人に訴えかけていたのかを丹念に、それこそ史料を1枚1枚めくるように解き明かしていくということなのではないでしょうか。
山田監督が幼いころ中国の大連で過ごして、戦後山口に引き上げてきたものの、山口ではどちらかというと差別や疎外に遭ってしまい、日本に故郷といえる場所を持っていなかった、ということは知りませんでした。あれだけ日本の景観を情緒豊かに撮りあげるかたなので、てっきり日本に郷里といえる場所を持っているのかと思っていました。
でも、よく考えてみると、日本に郷里といえる場所を持っていないからこそ、寅さんに、それこそ根なし草のように日本国中をまわらせて、各地の風光明媚な情景をカメラで切り取っていたのかもしれません。シリーズの最終話に近付くと北海道が舞台になることが多くなり、寅さん以外でも「幸福の黄色いハンカチ」や「遥かなる山の呼び声」、「学校II」、テレビドラマの「北の国から」など、北海道が舞台の映画に名作が多く、もしかすると監督は北海道に子供のころ過ごした大連の面影を追い続けていたのかもしれません。
そういった彼の作品、特に「男はつらいよ」シリーズは、高度成長期以前の日本とそれ以降の日本を明確に意識しています。葛飾柴又に住む寅さんの家族は前者の象徴で、シリーズが進んで現在に近づくにつれて現実とのギャップがもう手の施しようのないくらい大きくなってしまって、公害問題、過疎化問題、少子化問題、高齢化問題、様々な問題が日本の社会を覆っていく「未来」を彼は予見し、警鐘を鳴らし続けていたのです。
この本は、そういった山田監督の目を通した日本人観、日本史観を提示していきます。論としては理解できます。でも、わたしはなんでもかんでも高度成長期以前の方が良くて、日本は経済成長や近代化と主に大事なものを失った、とか、昔に戻らなければいけない、といった考え方には反対です(この本がそう主張しているわけではないと思いますが……)。
以前、時代劇を観たときにも感想を書きましたが、村社会、共同体社会というのは、確かに人情が深く細やかな仕組です。しかし、同時にそれは他人を監視して異分子をはじき出し疎外する仕組でもあります。仲間うちであればお互いを思いやり、面倒もみ、心配もします。しかし、仲間ではないと定義づけされた瞬間に、村八分、いじめの対象になります。
そういう少数の異分子たちを助けたのが経済的な豊かさです。お金があれば疎外された環境から脱出することができます。そうやって地方から東京に出てきたひとたちを、わたしは多く知っています。彼らは勉強し、技術を身に付け、自分の力で立ち上がり、自分の居場所を見つけ、あるいは創り出しました。
それを否定することは正しいことではありません。いま日本に蔓延しているさまざまな問題は、経済成長したことによる後遺症みたいな部分も確かにあると思います。しかし、それとは関係ない、そもそも日本人が内在している原罪のような習慣、旧態依然とした価値観に依ることも多いのです。
いじめ問題は経済成長やそれに伴う核家族化とは何の関係もありません。それこそ、高度成長期以前の村社会、共同体社会の残滓です。少子・高齢化問題もどちらかというと文明のフェーズの問題で、ミクロの問題でないと思います。貧困問題は経済政策、政治の失敗であって、60年代以降の経済成長が悪かったわけではありません。むしろ社会が豊かになれば解決する問題です。
この文章の冒頭でわたしが書いた寅さんシリーズを観なくなった理由というのが、ここにあることが分かったような気がします。わたしは無邪気に昔の方がいまよりよい、とは思うことができないのです。かりに、時間を巻き戻して子供のころに戻してあげる、といわれても、わたしは断ります。子供のころには、佐賀関での祖母との思い出や良い思い出もたくさんあります。しかし、もう一度あの時期をやり直すかというと、明確に「No」です。
この本は、もちろん山田洋次監督の足跡を辿り、その功績を再認識するためには非常によくできています。また、日本の戦後史を振り返ってみるためにも適した、優れた著作といえます。残念なのは、そういった良書が、日本人の手ではなくフランス人の手によって著されたということです。日本人がもし、この本で提示されている視点を持っていない、あるいは賛同するか反対するかはともかくとして、気にもしてないとするならば、そちらのほうがよっぽど問題だなと思いました。
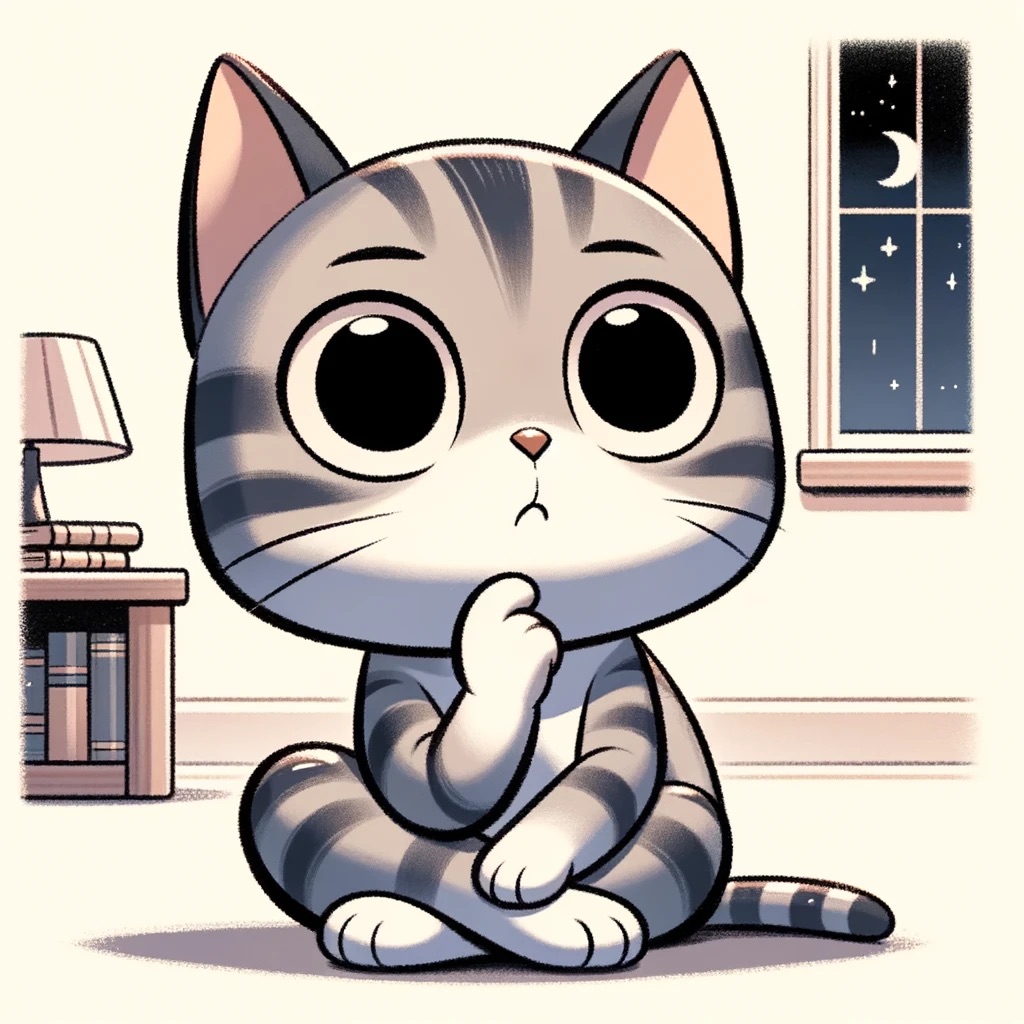


コメント