私が社会人になってから、ものすごい勢いでコンピューターが進化し、世の中のデジタル化の進捗には目を見張るものがありました。WindowsというOSが当たり前になり、インターネットが一部の研究者のものではなく、社会インフラとして普及し、いまやスマホやタブレットからスマートウォッチ、スマートリングなどデジタルデバイスも多様化してきています。
最近では、これらの流れに加えて、AIがかつてのインターネットのように一般化、社会インフラになりつつあります。この20年で情報量は爆発的に増え、その流通量ももはや人間が管理するには限界があると言えます。AIが出てくるのは必然と言って良いでしょう。
そんななか、我々人間の側がどうあるべきか、どのようにこのような状況に相対して生きていくのか、その議論もされるようになってきました。デジタルを捨てて60年前に戻ろうといった極端な議論から、さらにデジタル化を推し進めて人類として次の段階に行くと論ずるまた一方の極論まで様々です。
私もご多分に漏れず、この30年間デジタルの中で生きてきましたし、むしろそれを生業として生きてきました。デジタルのありがたさや素晴らしさは誰よりも分かっているつもりです。デジタルガジェットも大好きです。予算の許す限りApple製品は欲しいと思います。AIも複数のLLMを使って仕事をしています。ほんの1年前までは、仕事のプランもプライベートのプランも全てデジタルでした。
しかし、最近、歳を取ったこともあって、少し考え方が変わってきました。デジタルは今までどおり維持していきます。しかし、100%デジタル化することはあまり人間という生き物のにとって良いことではないのではないか、という気がしています。
この20年、凄まじいスピードで大量の仕事を私たちはこなしてきました。常に何かに追いかけられ、漠然とした不安と焦燥に駆られながら、駆け抜けてきました。その結果、出来上がった「私」という人間は、ストレスにまみれ、体重も120kgに達し、血圧は危機状態、いつ死んでもおかしくないと医者から言われるまでになってしまいました。
これは、私だけに起こっていることでしょうか? 周りを見てみると、そうでもないように見えます。私のように肥満し、ストレスを常に感じ、病気に苦しんでいる人々のどんなに多いことか。もちろん、デジタル化が進展する前もストレスはあったでしょうし、肥満をしている人も病気をしている人もいたと思います。しかし、自分の父親の世代を見ていると、我々とはその程度が違います。
私は、私たちの両親の世代は結構長生きするのでは無いかと思っています。一方で私たちは、医療技術が格段に進歩しているにもかかわらず、彼らほど長生きできないのではないか、そんな不安を感じているくらいです。
これは私の感覚なので、それが正しいと強弁するつもりもないですし、仮に正しいとしてもそれがデジタルだけが理由とは思いません。しかし、前にも書きましたが、この1年、ちょっと生き方を変えただけで、私の人生は大きく変わりました。何を変えたのか。それは、デジタルの依存度をちょっと減らした、ということです。
第1に、Twitter(現X)などのSNSを止めました。その結果、スマホを見る時間が激減しました。いまは、ダイエットに使っている「あすけん」というアプリを使ったり、バスや電車の時刻を見るために使うくらいです。
これによって、情報が自分の意図とは関係なく流入してきて、しかもその内容に精神状況を左右されるということが全く無くなりました。情報は自分が必要なものを自分で探しに行く。そういう当たり前のことができるようになり、それとともにストレスが大きく減りました。
第2に、仕事のプランニングをデジタルからアナログに変えました。具体的には別に書いた投稿を読んでいただきたいのですが、紙の手帳を使ってマンスリープラン、ウィークリープラン、デイリープランを作り、またブレインストーミングも紙の手帳で行うようにしました。
これによって、仕事の見通しが良くなり、全体像が頭の中に描けるようになりました。デジタルだけで管理していたときは、その情報が0か1かで、点しか見えなかったのです。それが、アナログにすることによって、線になり、面で管理できるようになってきました。これによって仕事のストレスが減り、就業時間外に仕事をする時間も激減しました。
第3に、電子書籍だけでなく、紙の本も読むようにしました。社会人になってからほとんど本を読むことがなくなってしまい、学生時代の本の虫が嘘のようだったのですが、紙の本を読むようになって、読書量が激増しました。
きっかけは以前書いたように、朝のウォーキングのときにKindleで本を読む習慣が付いたことです。しかし、それを弾みとして、朝以外の時間も本を読むようになりました。その際読むのは紙の本です。紙の本を読むようになって、本を読むスピードがKindleで読むよりも速くなりました。また、Kindleではときどき字面を追っているだけで中身が頭に入っていないということがたまにあるのですが、紙の本は全くありません。
第4に、デジタルデバイスを買う際に、そのデバイス自体を目的とするのではなく、そのデバイスを使ってどういうアウトプットをしようとしているのか、ということを考えるようにしました。今までは、新製品が出たら、予算の許す限り脊髄反射的にデバイスを購入しているようなところがありましたが、それがなくなりました。そのデバイスにどういう意味があるのか(当たり前のことではあるのですが)考えて買うようになりました。
これにより、お金を有効に使うことが出来るようになりました。本に使ったり、旅行に使ったり、それこそ萩の土地建物を買うために使ったり、今までの人生では考えられなかった人生のバリエーションが増えたような気がします。
今、朝のウォーキング時に読んでいる司馬遼太郎の『竜馬がゆく』の中で、坂本竜馬が戦艦の艦長として操舵するシーンが出てきます。竜馬は船の計器類を「機械の従者」と呼んでいたそうです。
「こいつをうまく使えば、自分がいまどこにいて、何をすべきかがわかる」
私は、これだ、と思いました。どんなにデジタルが進化しようと、AIが人間を越えていこうと、これらの「機械の従者」を使って、情報の海の中で自分の位置を知り、自分の判断をする。正しいか正しくないかではなく、その判断の結果に責任を負う。その決断と結果への責任をきちんと理解するために、予測するために、「機械の従者」たちを使わなければならないのではないでしょうか。
改めて申し述べるようなことでは無いのかも知れませんが、この1年の自分の変化を思うと、シンプルな結論ではありますが、こういった姿勢、デジタルとの関わり方が、人間としてまだマシな、ベターな生き方なのではないかなと思うのであります。
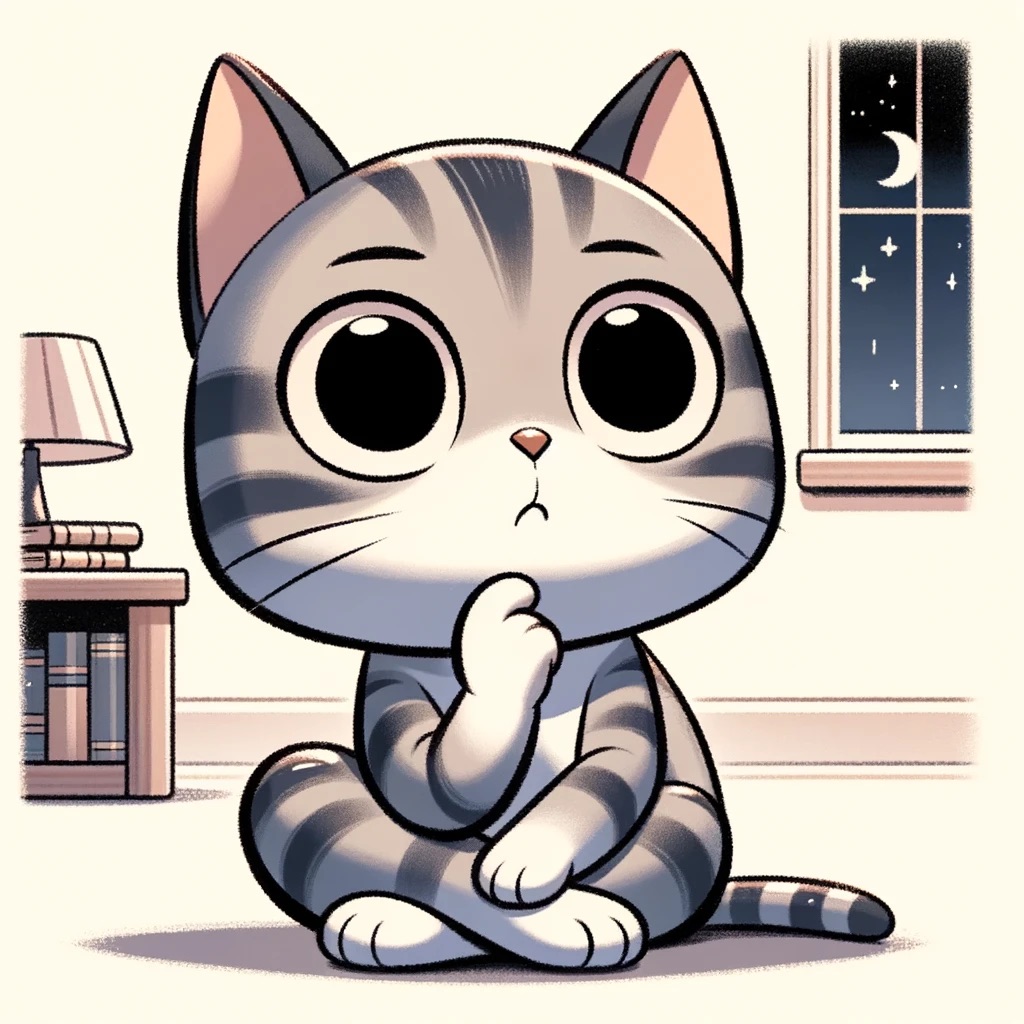


コメント