津本陽の『下天は夢か』を読了した。
今回で8回目くらいだろうか。以前、理想の物書きとして津本陽を挙げたとき、「夢」シリーズを読み直すことにしたのだ。
「夢」シリーズは、織田信長を描いた『下天は夢か』と豊臣秀吉を描いた『夢のまた夢』、そして徳川家康を描いた『乾坤の夢』の三部作をいう。
今回読了したのは、その最初、織田信長を描いたものになる。
今さら信長について書く必要はないと思う。戦国武将の中では上杉謙信に次いで好きな武将だ。
謙信と信長は対極にある。謙信は北方の守護神である毘沙門天の生まれ変わりとして軍神の名をほしいままにした。一方信長は、徹底的な合理主義のなかで既存の宗教的権威を打破し天下布武を図った。
なぜ、対極にある二人が好きなのか。
謙信は政略や謀略を嫌ったと言われる。彼は至誠を重んじ、自分の信ずるところに従った。日本的な情実によって物事の判断をしなかった。当時から自分に厳格すぎるという批判があったほどだ。
信長は旧弊な体制を嫌い、破壊した。彼の行動原理は合理性だ。
統治能力を失った足利幕府だけでなく、旧弊で堕落していた宗教界も破却した。農民たちを束縛していた村社会を壊して物流や経済圏の改革も行った。
本能寺での最後を迎えるころには自らを神とするようになったともいわれるが、それも過去のしがらみにとらわれない徹底した中央集権体制を確立するためではなかったろうか。
私は、謙信の至誠を重んじる生き方、信長の合理性を重んじる考え方が好きなのだ。
至誠と合理性は矛盾した言葉のように聞こえる。しかし、その矛盾こそが人間の本質だと思う。
至誠を貫こうとすると合理性に反する場面もある。合理性を重視すると誠を裏切ることもありうる。しかし、大事なことは、それぞれの局面で考え、悩み、決断し、その結果に責任を負うことだ。
謙信も悩んだ。悩んだ挙げ句に僧形となり春日山城を出奔した。彼は至誠と現実の政治のギャップに苦しんだろう。
信長は悩まなかったろうか? いや、悩んだろう。彼は心を鬼にして合理性に従ったはずだ。
一向一揆を弾圧したとき、相手は僧だけではなかった。無辜の農民もいたのだ。しかし彼は、宗教的権威を打破し天下布武を実現するためには、農民の心の中にある非合理的な来世への期待そのものを打ち砕く必要があった。
彼らは、自分の信じるもののために戦い、妥協しなかった。そして、その結果がどうあれ、言い訳はせずに責任を負った。
信長が本能寺を生き延びていたら、どうなっていただろう。
信長の時代、日本は銀の生産量は世界の約3分の1を占める有数の産出国だった。その冨を背景に、徹底した合理主義に基づく中央集権体制が、天下布武が達成されていたら、日本は世界のどの国よりも先に近代化していた。
異なる作品の中であるとはいえ、こういった一見矛盾した価値を書くことは難しい。作者が主人公に感情移入してしまえばなおさら困難になり、その作品は説得力を失う。
しかし、それを津本陽は書いてしまう。何故か。
津本陽は謙信が何を感じたか、信長が何を思ったか、詳細に書き連ねることはしない。彼らの感情や想いは最小限だ。綿密な史実の調査と、事実を客観的に丹念に記述していく。この「抑制と具体性」が、矛盾した価値を書くことを可能にしている。
書きすぎない。抽象的にならない。だからこそ、彼の文章は私たちにいろいろなことを示唆し、考えさせてくれる。私の理想の「物書き」の姿がここにあるのだ。
「夢」シリーズは、読むたびに異なる思索に誘ってくれる。新たな気づき、新たな自分を見つけることができる。それが読書の楽しみであり、そういう文章を書くことが、物書きの醍醐味なのではないだろうか。
小説を書いていると、ついつい登場人物の内面について書きたくなる。あたかも自分の心であるかのように雄弁になってしまう。しかし、そこをグッと堪えて、書きすぎず、抽象に逃げず、読者に考える余地を残す文章を書きたいと思う。

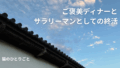
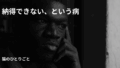
コメント