今朝は習慣にしている朝の散歩ができなかった。
午前6時、営業の運転する車に乗り込んだとき、いつもの時間に歩いていないという事実が、妙に落ち着かない気持ちにさせた。
大分への出張である。水分峠を越え、車窓には緑の山々が流れていく。10月らしい天気で気候も爽やかだった。3時間近い道のりだが、不思議と退屈しない。
隣で運転している営業は仕事ができる人だ。話していて飽きない。仕事の話をしてもプライベートの話をしても面白い。それは彼が持っている少し特別な力によるものだと、車中で気づいた。
彼は人間に対する興味がとても強い。常に人を観察し、その人にとって何が良いか、どう進めれば物事がスムーズに進むのかを描くことができる。
話を聞いていると、彼が相手の立場に深く入り込んでいることが分かる。どっぷりと、という表現が正しい。相手の感情に染まることで、相手が何を必要としているかが見える。だから人が動く。仕事が進む。
羨ましいと思った。
私は物書きなのに、人間に興味が持てない。そう自分を評価してきた。それは短所だと思っていた。しかし、この営業と一緒に3時間を過ごしながら、自分の認識が正確ではなかったかも知れないと思い始めた。
私は人間に興味がないわけではない。見ている。観察している。ただ、染まらないのだ、と。
私は人の影響を受けないようにしている。相手の感情や本質を見ながらも、そこに自分を浸さない。透明な壁を一枚隔てて、常に少し外側にいる。
それは子供の頃から身につけた技術だった。煩雑な人間関係や利害関係から自分を守るために、無意識のうちに習得したのだと思う。人間の感情に染まらないこと。それが自分を守る唯一の手段だった。
そして気づいた。それは書くときにも働いている。書く対象に対しても、私は距離を保とうとする。抑制と客観性。それが私のスタイルだと思ってきた。しかしそれは、選んだスタイルというより、染まることができないという性質なのかもしれない。
この営業との三時間でさえ、私は観察していた。彼の熱量を感じながら、その熱に染まることなく、彼がどのように人に興味を持ち、どのように入り込んでいくかを見ていた。
染まらないことの代償は、孤独である。
人との真の繋がりは、どこか希薄だ。いつも透明な壁の向こう側にいる感覚がある。この営業は人の中にいる。私は人の外にいる。それは「抑制と客観性」というスタイルを大事にするという点では武器になっているかもしれない。しかし同時に、決定的な欠落でもある。
染まることができたら、もっと深く人を理解できるのだろうか。もっと血の通った文章が書けるのだろうか。そんな問いが頭をよぎる。でも、染まることはできない。それは今更変えられない自分の在り方だ。
車窓の緑は変わらず流れていく。営業は熱心に次の訪問先の話をしている。朝の散歩ができなかった落ち着かなさは、いつの間にか消えていた。なぜなら、観察すべきものがここにあったからだ。
染まることはできない。でも、見続けることはできる。それが私のやり方だ。孤独であっても、観察者として在り続ける。

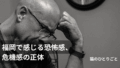
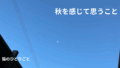
コメント