外資系企業の日本法人の社長とは何か。
本社のCEO、COO、CRO、CTOといった経営陣と、日本側の出資者、顧客、社員——それぞれの利害を調整しながら、会社を立ち上げ、ビジネスを推進していく。仕組みを作り、結果を出し、休みなく働く。それが外資系日本法人の社長だ。
特に日本に進出して間もないベンチャー的な組織であれば、整った仕組みなどあるはずもない。本社と現地、顧客と社内、さまざまな立場の人々の間に立ち、調整を続けなければならない。成果を出しても、それを適切に説明できなければ評価されない。
外資系日本法人の社長という仕事をもう少し掘り下げてみよう。
まず、ステークホルダーが多い。その調整こそが仕事の重要な部分を占める。本社の経営陣、日本側の出資者、顧客、社員。それぞれが異なる期待と利害を持っている。その間に立ち、対話を重ね、落としどころを見つけ、組織を前に進める。それが社長の責務だ。
ステークホルダーたちをマネージし、ビジネスを推進して売上を上げていくことは並大抵のことでは無い。休みは取れないだろう。私は日本企業の経営者も何人か知っているが、彼らは一様に働き過ぎだ。24時間365日働き続けている。
ある経営者は私に言った。自分が立ち止まるとビジネスが止まる。会社が止まる。従業員やお客様、株主に迷惑をかける。彼らは、止まりたくても止まれないのだ。そういうギリギリの修羅場で生きている。
外資系日本法人の社長の仕事でもう一つ大事なことは、本社への説明責任である。本社の経営陣と密に情報を共有し、議論する必要がある。結果が良かろうと悪かろうとだ。むしろ悪い場合には、計画と実績のギャップを分析し、原因を特定し、対応策を提示して次のアクションと結果をコミットしなければならない。数字だけを報告するのではなく、背景にある市場の状況、競合の動き、組織の課題を説明し、理解してもらう必要がある。国も文化も違う人間が相手だ。これも容易な仕事では無い。
私は日本企業のマネジメントの大部分は、外資系日本法人の社長には向いていないと思う。何故なら、彼らは経営者では無く、大企業の「中間管理職」であることが多いからだ。経営者と中間管理職では役割も求められることも全く違う。
大企業の中間管理職の感覚を引きずっていたのではダメだ。
中間管理職の仕事は、与えられた枠組みの中で成果を出すことだ。組織の仕組みは既に存在し、上司がいて、部下がいる。ステークホルダーとの調整も、ある程度はルール化されている。自分の裁量は限られているが、その分、責任の範囲も明確だ。
だが、社長は違う。特に外資系日本法人の社長は、すべてを自分で作らなければならない。仕組みがないなら作る。ステークホルダーとの関係も、ゼロから構築する。誰も指示してくれないし、誰も助けてくれない。すべての責任は自分にある。
トップとミドルの決定的な違いは、ここにある。
社長という役職には、確かに魅力がある。経験を積み、キャリアの集大成としてトップに立つ。それは誰もが憧れる道だろう。だが、役職の響きと、日々の実務は別物だ。
では、どういう人が外資系日本法人の社長に向いているのだろうか。
まず大事なことは、社長という仕事は「やらされる仕事」ではない、ということだ。
中間管理職であれば、上司から指示を受け、それを実行することが仕事の中心になる。だが社長は違う。自ら判断し、自ら動き、自ら責任を負う。誰かが道を示してくれるわけではない。
もしあなたが社長職を打診されたとき、まず問うべきは「この仕事の本質を理解しているか」だ。肩書きや報酬に目を奪われず、日々何をしなければならないのか、どんな困難が待っているのか、冷静に見極める必要がある。
次に、自分の器を知ることの重要性だ。
向いていない仕事を無理に引き受けると、本人も不幸だし、組織も不幸になる。社長職は、誰にでもできる仕事ではない。ステークホルダーとの調整、仕組み作り、休みなく働く覚悟。それらすべてを引き受けられるかどうか、自分に正直に問いかけるべきだ。
もし自分には向いていないと感じたなら、断る勇気も必要だ。断ることは、逃げることではない。自分の限界を知り、適切な判断をすることは、むしろ誠実な態度だ。
そして最後に、もしあなたが社長職に就くと決めたなら、覚悟を決めることだ。
少なくとも2〜3年は全力で取り組む覚悟を持つべきだ。その間、すべてをこの仕事に捧げる。ステークホルダーと徹底的に対話し、仕組みを作り、結果を出す。それができないなら、最初から引き受けるべきではない。
外資系日本法人の社長は、確かに難しい仕事だ。だが、その難しさを理解した上で、それでも挑戦したいと思える人だけが、その椅子に座るべきなのだ。
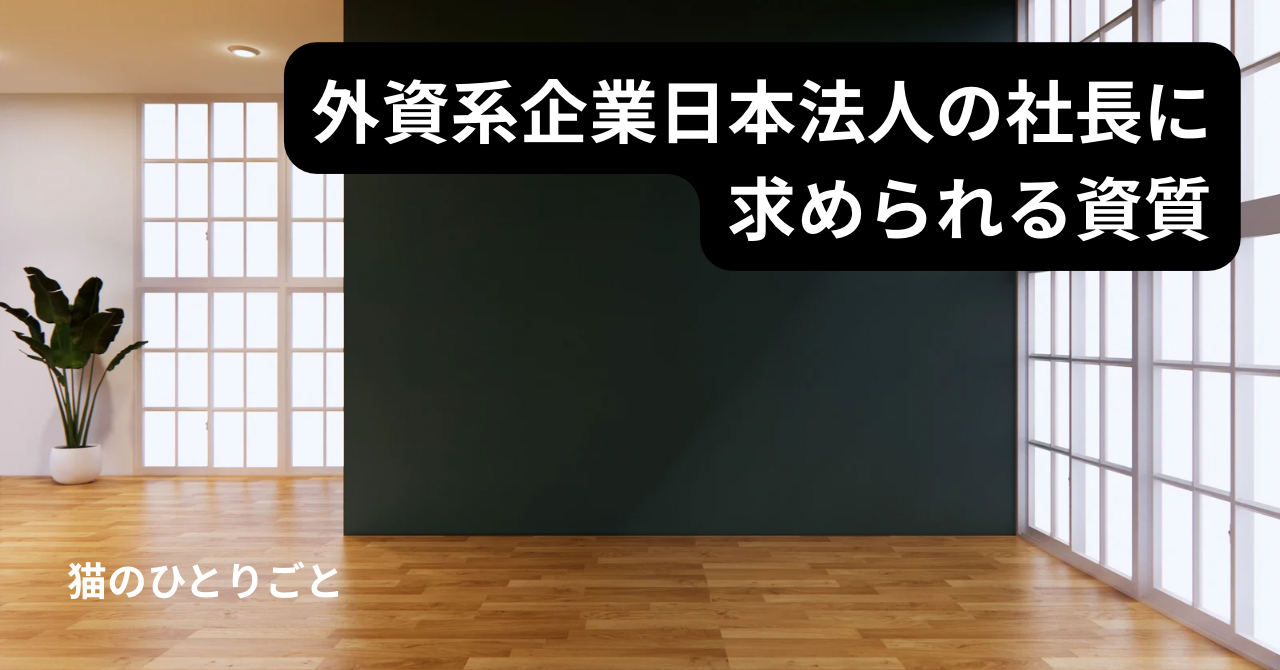
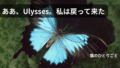
コメント