萩の地で萩の花を探すなど、あまりにも自明なことのように思えるかも知れない。しかし私はどうしても萩で萩の花が見たかった。今書いている小説のファクトチェックにもなるからだ。
九月も終わりに近づいた早朝、私はいつものように散歩に出かけた。萩の花を探すと心に決めていた。秋の七草の筆頭を飾る萩の花が、今まさに見頃を迎えているはずだった。萩という地名そのものが、かつて「萩がたくさん生い茂った山があった」ことに由来すると聞いたからだ。
午前5時、菊ヶ浜から歩き始める。日本海からの風が少し寒いくらいだった。
指月公園へと足を向ける。毛利輝元公の銅像が、まだ暗い空に向かって立っている。この殿様は萩の花をご覧になっただろうか。慶長九年、広島からこの地に居を移した輝元が三角州に築いた城下町は、確かに「萩」と名付けられた。だとすれば、この地には萩の花が咲き乱れていたはずではないか。
指月公園の奥で、暗がりに何かがありそうな気配を感じた。しかし確認するには暗すぎた。昼間に再び訪れれば答えは出るだろう。だが私は、その確認を「次の機会」に委ねることにした。
西の浜墓地を抜け、天樹院墓所を経由して、鍵曲の道に入る。しかし、萩の花を見つけることができない。「江戸時代の地図がそのまま使える」と言われるこの町並みを歩きながら、私は一つの皮肉に気づいていた。町の構造は四百年前のまま保たれているのに、地名の由来となったはずの植物は、なぜか姿を見せない。
石垣は残り、武家屋敷は保存され、先人の銅像は各所に建っている。しかし、この地を「萩」と名付けた理由そのものは、現在の住宅地の片隅のどこにも見当たらなかった。
平安古の界隈を抜け、春日神社に向かう。少しずつ白い光が増していく中で、小さな花影を見つけるたび、期待で胸が躍った。しかし近づいてよく見れば百日紅だった。次は確実にと思えば、ムクゲだった。期待と落胆を繰り返すうち、自分が探している萩の花の具体的な姿を、実は正確に把握していないことに気づいた。
道すがら、私は指月公園での自分の選択を反芻していた。真実よりも可能性を、現実よりも想像を選んだのだ。高杉晋作の銅像を見上げ、木戸孝允邸の前を通り過ぎ、田中義一の像に別れを告げて私は自宅への道を急いだ。
後で調べてわかったことだが、萩市では指月公園や松陰神社などの特定の場所に萩の花が植栽されているものの、一般的な住宅地での自生は少ないという。つまり、私の体験は決して特異なものではなかったのだ。
しかし、それでよかったのだと思う。もし町角のそこここに萩の花が咲いていたなら、この散歩はただの花見で終わっていただろう。見つからなかったからこそ、私は地名と現実、過去と現在について考えることができた。時の流れという名の変化の中で、何が残り、何が失われていくのかについて思いを馳せることができた。
萩の地で萩の花を探した朝は、見つからなかったからこそ意味があったのかもしれない。指月公園の暗がりに残した可能性は、今も私の中で静かに息づいている。次にこの町を歩くとき、私はまた期待を胸に、あの暗がりを覗き込むだろう。そしてそのときもまた、確認を先延ばしにするのかもしれない。探すことの豊かさを、もう少し味わっていたいから。

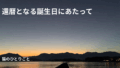
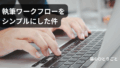
コメント