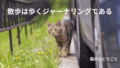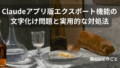私は数えで61歳になる。本厄だ。
本来であれば正月に厄払いをしなければならないが、少々行き違いがあり前厄の厄払いを8月にしたこともあって、相方と一緒に昨日行ってきた。
行ったのは「厄八幡」として親しまれており、全国的にも有名な厄除け神社である「若八幡宮」だ。
若八幡宮は博多駅の北西、御笠川の近くに位置する。近くには祇園駅もあり、周辺には寺社が多い。櫛田神社とも目と鼻の先だ。
創建年は不明だが、元禄年間(1680〜1704年)に編纂された貝原益軒の「筑前國続風土記拾遺」に記載があり、かつては「藪八幡」と称していた。
ご祭神は大鷦鷯命(オオササギノミコト・仁徳天皇)、大巳貴命(オオナムチノミコト)、少彦名命(スクナヒコナノミコト)。主なご利益は国家安寧、商売繁盛、五穀豊穣、殖産振興、縁切りなどと言われる。
決して大きな神社では無い。しかし、若八幡宮での年越しの厄参りは博多の年越しを象徴する名物行事で、厄年の人だけで無く広く市民が参加している。
この暑い時期に厄払いをするのは私たちくらいのものかと思っていたら、他にも数人受ける人たちがいた。昨年は確か、私たちだけだったと記憶している。
ちょうど儀式が始まるところだったので、寒いくらいに冷房の効いた部屋で待つのは数分だった。
儀式は、詰め込んで20名がやっと入れるくらいの小さな空間で行われる。時間にしておよそ20分。基本的には宮司の指示に従って拝礼を行う。
儀式が終わると御札や御神酒、お箸やお菓子の入った袋をいただく。御札を受け取るとき名前を確認するのだが、私の名前が一文字間違っていたので、訂正してもらった。
厄払いというのは、心の保険のようなものだと思う。保険をかけることで人は安心を得られる。実際に事故や病気が降りかかって来なくても、人は保険をかける。
厄払いも同じようなものだ。実際に何か危難が降りかかってくるかどうかは分からないが、厄払いをすることで人は安心を得る。
厄というものはその時だけ払えば良いものではない。ある日突然やって来て人を苦しめる類いのものではない。
日ごろの行い、生活の積み重ねの中で、少しずつその不徳が溜まっていくものなのだ。日々の生活を疎かにして、年に一度厄を祓ったところで、禊ぎが終わるわけがない。
しかし、とは言え、厄年なのに厄払いをしないのも気持ちが良いものではない。
日ごろの生活一つ一つを丁寧に誠実に、感謝しつつ暮らしていく。特に徳を積む必要は無いが、不徳を溜めないようにする。それでも溜まってしまう不徳を年に一度払っていただく。
厄払いというのは、そういった心の安心のために行うものなのだと思う。「厄八幡」での年越しの厄参りに厄年では無い人たちも広く参加しているのは、共同体としての禊ぎ、払いを通して、地域に住む人々の心の安心を得るためなのでは無いだろうか。