わたしの現在の執筆環境は、アイディア整理はDrafts、執筆とファイル整理はObsidian、バックアップはGitを使っています。
エディタはObsidianでも十分なのですが、ひとつだけ不満がありました。
執筆中に、ちょっとしたファクトチェックをしたいときに、Obsidianのエディタでは、ちょっと面倒なのです。
いちいちClaudeアプリに移動してわざわざセッションを開いて聞かなければなりません。その行ったり来たりが微妙にストレスになっていました。
そこで、Cursorというエディタを使ってみることにしました。
Cursorは、Obsidianのエディタと同じように、Markdownファイルを編集できます。また、Gitと連携することで、ファイルを保存すると、自動的にGitにコミットさせることもできるようです。
導入の難易度はそれほど高くありません。Obsidianをお使いの方なら問題なくインストールして使うことができるでしょう。
細かい設定をやろうとすると、この手のツールによくあることですが、かなり細かいところまで設定できますので、使いながら、必要に応じて設定を変えていく、というやり方がよいでしょう。
面白いのは、エディタの横にAIとのチャットペインが開いて、チャットできることです。ChatGPTだけでなく、ClaudeやGeminiなど、様々なAIとチャットできます。わたしはClaudeを選びました。
執筆しながら、調べたいことがあれば、いちいちClaudeのアプリを開くのではなく、このチャットでやり取りをします。
Cursorは基本的に無料で使えますが、AIの利用度合いによって有料にする必要があります。わたしは、いまは無料プランで様子を見ています。
- 無料プラン: 月間200回の基本的なAIリクエスト
- Pro プラン: 月額$20で無制限利用(より高性能なモデルへのアクセス含む)
- Business プラン: チーム向け
Cursorに附属しているClaudeは、わたしが既に契約しているものとは別のものです。
いままでわたしがClaudeと構築した資産をそのまま使うことはできなさそうなので、ちょっとした一時的な確認事項、調査事項のために使うことになりそうです。
但し、まだ本格的にCursorについて調べたわけではありませんので、もしかしたら適切にプロンプトを書ければ、わたしが以前構築したObsidianとClaudeとの連携のように本格的に原稿をレビューしてもらうこともできるようになるかも知れません。もう少し、試行錯誤が必要かなと思っています。
いずれにせよ、既にAIサービスと契約されている方は、ユースケースがダブらないように気を付けてください。
もう一つ面白いのは、執筆中に文章を書いているときに、次に書くべきテキストの候補を出してくれることです。候補を使いたければタブキーで確定します。
確かに面白いのですが、正直精度はいまひとつです。
例えば、テキストを書いている最中にそのあとの予測をしてくれますが、自分の書きたい内容やニュアンスに合ったものが出てくる確率は、体感で1割程度でしょうか。
また、せっかく出してくれている候補で、思考が邪魔されたり、書こうと思っていた表現を候補の影響を受けて忘れてしまったりすることもあります。
この後精度が上がってくるかもしれないので、このまましばらく使い続けてみるつもりですが、邪魔になるようでしたら、機能をオフにするかも知れません。
エディタの書き心地自体はとても良いです。以前プログラムを書くときにVS Codeを使っていたのですが、それと同じような書き心地です。
今回はソースコードを書くわけではないので、フォントも日本語がしっかりと美しく表示される「游教科書体」を使っています。
これでわたしの執筆環境は下記のような構成になりました。
- アイディア整理:Drafts
- 執筆:Cursor
- ファイル整理:Obsidian
- バックアップ:Git
正直言うと、CursorとObsidianの使い分けがまだできているわけではありません。
例えば、CursorからAIだけでなく、Gitへのコントロールとか、Wordpressへの投稿やnoteへの投稿などのアクションを取る方法がまだ分かっていません。
これらができるのであれば、完全にObsidianは「保管庫」としての役割だけにできます。
今後使い続けながら、使い分けの道を探っていきたいと思います。
この環境で執筆の効率がどれだけ上がるのか、運用してみるのが楽しみです。

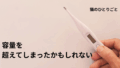

コメント