わたしは朝5時に起きます。これは平日でも休日でも変わりません。起きて顔を洗って、歯を磨いて、トイレに行って、猫にごはんをあげてから散歩に出かけます。
散歩は福岡と萩でもだいたい60分から70分。距離にして5キロメートルから6キロメートルほどです。この距離を早歩きで、とは言っても、途中で良い風景に出会えばiPhoneで写真を撮りますし、萩ではゴミ拾いをしながら歩いているので、それほど真剣にウォーキングしているというわけでもありません。
福岡でも萩でもわたしの散歩ルートはほぼ決まっています。朝の時間は貴重なので、ハプニングがあるとその日の予定に影響を与えます。なので、特に平日のルートは変えません。休日であれば、ちょっと寄り道してみようとか、冒険をすることもなくはないです。今日は、萩の散歩ルートについてご紹介しましょう。
スタート地点は、菊ヶ浜です。菊ヶ浜は北長門海岸国定公園内に位置する、白砂青松の海岸として有名な海水浴場です。環境省の「快水浴場百選」に選ばれるほど水質が良く、海の透明度が高いことで知られています。また、日本の夕陽百選にも選ばれるほどのすばらしい景観を楽しむことができます。
場所は国指定史跡「萩城跡」の東側に位置していて、左手に指月山と石垣、右手には笠山、後ろには松林という絶景です。指月山には1604年に毛利輝元が築いた萩城(別名:指月城)があったことは言うまでもないことですね。2015年に「明治日本の産業革命遺産」として世界遺産に登録されています。
菊ヶ浜の松原は、「阿武の松原」として「金葉和歌集」にも詠まれているとおり、とにかく景色が最高で、沖合いには笠山や多くの島々を眺めることができ、夕景だけでなく、朝の景色も美しい絶景スポットと言えます。今はまさにその季節で、晴れた日には山の緑と空の青、そして砂浜の少し黄味がかった白が、眩しいほどのコントラストを作り出しています。
次に向かうのは、萩城跡。指月公園の中にある志都岐山神社に行って、朝の参拝を済ませます。志都岐山神社は明治11年(1878)、萩町及び付近の有志が発起し、萩城跡本丸内に山口の豊永・野田両神社の遥拝所を創建したものです。翌12年に指月神社と称し、明治15年県社に列せられ、志都岐山神社と改められました。毛利元就、隆元、輝元、敬親、元徳の五柱を祭神として、初代から12代まで萩藩歴代藩主が祀られています。
深い木々に覆われた場所にあり、毛利家の家紋があちこちに見られます。社前の池にかかる石造りの万歳橋は、かつての藩校明倫館の遺構で、現在は渡ることはできません。ここには、萩でしか見られない桜「ミドリヨシノ」があります。ソメイヨシノに似ていますが、ガクが緑色で花びらは純白色、緑色のガクとのコントラストがとても綺麗です。山口県の天然記念物に指定され、根元の幹周1.7m、樹高6m、推定樹齢が100年あまりもあります。
ここは、散歩ルートの中で最もわたしが霊気を感じる神域と言えます。ここに来ると鳥肌が立つほど冷え冷えとした気持ちになります。夏の早朝とはいえこれほどひんやりとした空気を感じるのは、尋常では無いと思います。恐らく、指月山の森の深さも影響していると思います。深山幽谷を訪れたときに感じる神秘感、静謐感、神聖感と同じものを感じます。
次に向かうのは、毛利輝元像。萩城二の丸南門跡のところに建てられています。輝元はこの萩城を築城した人物で、毛利元就の孫にあたります。関ヶ原の戦いで西軍総大将として負けた責任を取らされ、領地の2/3と広島城を取り上げられた後、萩に拠点を変え萩城を築城し城下町づくりを進めました。今年は毛利輝元公没後400年にあたり、4月27日に萩城跡指月公園をメイン会場にイベントが実施されました。
毛利輝元に朝の挨拶をした後は、西の浜墓地に向かいます。萩市が管理する公営霊園のひとつで、萩市に本籍または住所があり、祭事を主宰し、他に墳墓の場所を得ることができない方が使用することができるようです。
ここは海も近く、浜風も吹いてくる静かな場所です。ここで手を合わせ、この場所で生まれ、生き、亡くなった方々に、いまここに住めることを感謝しています。非常に心が落ち着くところで、個人的には好きな場所なのですが、ときどき裏の林側にゴミが捨てられていることがあって悲しい気持ちになります。ゴミは大きなものでなければ、持ち帰っています。
そのまま海を右手に見ながら、向かうのは萩城下町の要とも言える鍵曲(かいまがり)の道です。鍵曲とは、左右を高い土塀で囲み、道を鍵の手(直角)に曲げた独特な道筋のことです。城下に進入した敵を迷わせて追い詰めるための工夫の一つで別名「追廻し筋」と呼ばれています。見通しがきかないクランク状の路を高い壁で囲い、一見行き止まりに見えるようになっているのです。
萩には鍵曲の造りの遺構がいくつかありますが、わたしが散歩しているのは平安古の鍵曲です。藩政時代、堀内地区に屋敷を構えていた重臣たちは、堀内が手狭になったことから新たに平安古(ひやこ)地区に下屋敷を求めました。その重臣たちの屋敷を守るために造られたものです。
歩いていると文字通り自分がどこにいるか分からなくなります。いまはもうさすがに慣れましたが、最初のうちはうろうろしてしまいました。城下町というのは道が整然としていて分かりやすそうという印象があるのですが、鍵曲は実際に歩くとかなり迷います。同じような白壁の通りの所々に丁字路などを配し、わざと迷わせるように造られているわけです。時代劇の一場面に迷い込んだような、不思議な気分にさせてくれる場所です。
鍵曲を抜けて平安古橋を渡ります。萩城三の丸から城下町に出入りする総門は北・中・南の3つがありました。南は平安古の総門と呼ばれ、外堀に架けられた玄武岩製の石橋・平安古橋が現存しているのです。平安古町に通じている橋というところから平安古橋と呼ばれています。外堀の周囲に位置する平安古・城下町は中下級武士・町人が住み、御成道には豪商が軒を連ねていたそうです。
次に向かうのは、春日神社です。奈良市の春日大社の御分霊を大同二年(807年)、萩椿郷在住の国守が萩の地に移したものだそうです。毛利輝元公が萩を居城とする際に防長二州の祈願所と定め、慶長13年(1608年)3月、社殿を堀内の現在地に建立しました。神社前の道には桜並木があり、春になると神社の中一面に桜が舞い散る風景が見られます。
宮司の方が毎朝境内を掃き清めておられます。宮司さんに挨拶をしてから、参拝します。最近では毎日顔を合わせるので、ちょっと世間話もするようになりました。わたし以外にも、何人かの方々が散歩中に訪れて手を合わせていました。
次に向かうのは、高杉晋作立志像です。晋作については説明不要ですよね。銅像は晋作の誕生地の近くにある「晋作公園」にあります。晋作が明倫館や松下村塾に通っていた20歳頃の若々しく凛々しい顔をイメージしており、両刀を差した羽織、袴の立ち姿で立っています。ざんばら髪ではない、髷を結った姿なので、わたしたちのイメージする晋作像とはちょっと印象が違います。革命の若き志士というよりは古風な武士に見えます。
高杉先生に朝の挨拶を済ませたら、次は青木周蔵、木戸孝允の生家に向かいます。青木周蔵はシーボルトに師事した日本屈指の蘭方医です。早くから種痘法に注目し藩内で施行していて、高杉晋作が10歳のとき疱瘡にかかった際、診療した医者としても知られています。
木戸孝允も説明は不要でしょうか。桂小五郎と言った方が分かりやすいかもしれません。慶応2年、坂本竜馬の仲介のもと薩摩藩の西郷隆盛や大久保利通らと”薩長同盟”を結び明治維新に尽力し、「維新の三傑」の一人とされています。
木戸孝允旧宅は、中に入ることができます。わたしは仕事に煮詰まったときによくここを訪れます。夕方5時まで開いているのですが、その30分ほどまえだとほとんど観光客はいません。その時間帯に上がり込んで、座敷の座布団の上で正座します。そこで5時まで思索に耽るというか、ぼうっとしています。自分が木戸たちが生きていた時代に迷い込んだような、自分が日本の歴史の流れの中にあることを改めて感じさせる場所です。
木戸孝允旧宅が面している通りを過ぎると、町人街に出ます。菊屋横町とも呼ばれ、萩藩の御用商人として約400年の歴史を持つ豪商菊屋の屋敷があるところです。国指定重要文化財でもあるこの屋敷は、約2,000坪、現在約3分の1が通常公開されています。白いなまこ壁が江戸時代の景観を残していて、商家建築と武家建築が混在する独特な街区と言えます。
その通りを真っ直ぐ抜けて田中義一像に向かいます。田中義一は第26代(昭和2年・1927年~昭和4年・1929年)内閣総理大臣です。軍人としても有能で、日露戦争時には満州軍参謀として児玉源太郎のスタッフを務めました。総理大臣時代には金融恐慌を鎮静化し、普通選挙法を施行した一方で、張作霖爆殺事件の責任を取って総辞職したことで知られています。
田中先生に挨拶をしたら、あとは家まで一直線です。いかがでしたでしょうか。毎朝、萩の観光ツアーをしているような散歩道でした。毎朝こういった場所を訪れることができるという、幸運に感謝しないではいられません。足腰が立つうちは、毎日、毎朝、この町を歩いていきたいと思います。
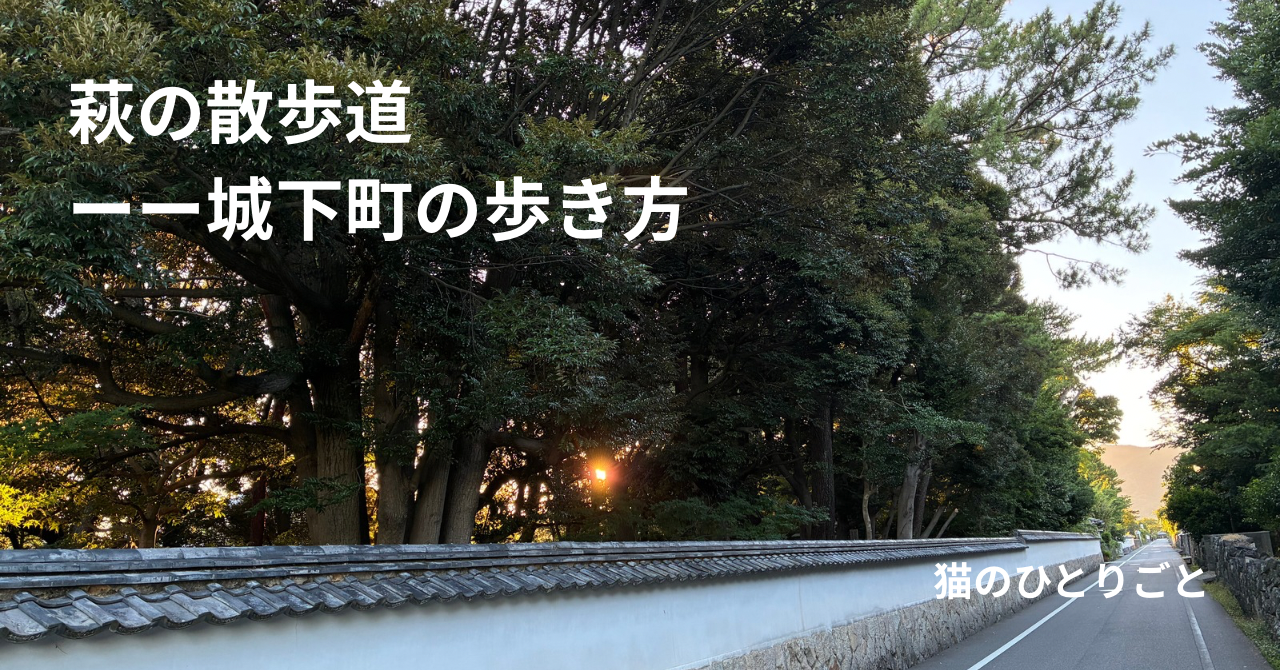

を観て思ったこと-120x68.png)
コメント