昨日から発熱しています。朝は平熱だったのに、夜になって38℃を越えてしまいました。頭が痛くて、鼻の奥に鈍痛がします。咳も出ますし、痰が絡むようになりました。
体の奥に鉛のような重さが沈んでいて、起き上がる気力すら持てない。昨日の夜から、まさにそんなふうにして、布団に沈んでいました。
不思議なことに、そういうときに限って、猫たちがそっと寄り添ってきます。
黒猫の歩は、わたしの足元でゴロンと横になり、背中を脚にぴったりとくっつけて眠りました。その大きくて柔らかい背中からじんわりと温かさが伝わってきます。言葉ではなく、ただ「ここにいるよ」という、静かな存在の主張です。
キジトラの七海はもっと直接的でした。ふわっと乗ってきたと思ったら、お腹の上に香箱座りをして、じっと動きません。まるでわたしの体調の悪さを封じ込めるように、そこに居座ってくれました。普段なら重いと感じるのですが、昨晩は不思議と、その重さが安心につながりました。
こういうことは、前にもありました。
五輝がいた頃。
わたしが仕事でどうにもならない苛立ちにまみれていたとき、彼は何も言わずにそばに来て、お腹を見せて横になりました。「撫でよ」とでも言うように。その丸まった体を撫でながら、わたしは自分の呼吸が静まっていき、苛立ちや疲れが遠のいていくのを感じていました。
猫はなぜ、気づくのでしょうか。人間の不調や、感情のさざ波を。目に見えないはずの「気配」を、まるで匂いを嗅ぐように察知して、そっと傍にいます。慰めるでも、励ますでもなく、ただ「共にいる」のです。
もしかしたら、人間は、言葉を持ったことで何かを失ったのかもしれません。語らずに伝える力。気配に耳を澄ませる感性。そういうものを、猫たちは変わらず持っています。
病んでいるとき、孤独なとき、心がこわれそうなとき——わたしのそばには、いつも猫がいます。
猫が人間の不調に気づくのは、嗅覚や聴覚の鋭さだけでは説明がつきません。明確な根拠があるわけではないけれど、彼らの「感応力」は、たぶん人間の思っている以上に豊かで複雑なのではないでしょうか。
もしかすると、彼らは人間の「波長のゆらぎ」を感じ取っているのかもしれません。いつもと違う呼吸のリズム、声のトーン、動きの緩急、あるいはただ座っているだけの姿勢の“違和感”。そうした些細な変化を、「情報」ではなく「気配」として感じているのでしょう。
それに比べて、わたしたちはどうでしょう。誰かの不調に、どれほど敏感に気づけるでしょうか。SNSの投稿が減ったから、口数が少なくなったから。そんな表層的な兆候に頼っている限り、本当の異変には触れられないのだと思います。
猫たちのように、ただ静かにそばにいるという選択肢。それは、言葉よりも深いコミュニケーションかもしれません。「寄り添う」という言葉が、いちばん似合うのは、やっぱり猫たちの行動です。
五輝のぬくもりは、もう触れることはできないけれど、歩と七海の中に、確かにその面影が宿っています。病んだわたしにそっと寄り添ってくれた、あの記憶の続きが、今も生きているのです。

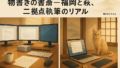
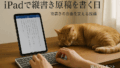
コメント