数年のあいだ、小説を書くことができませんでした。書けない、書くことがない、読むことすらできない。そんな状態がこの数年続いていたのです。
わたしが生まれて初めて小説を書いたのは高校生のときですが、本格的に長編を書いて新人賞に原稿を送るようになったのは社会人になってから、それもかなりあとになってからです。たしか、2013年から2015年のあいだでした。
当時「デモンズソウル」というゲームが大好きで、その世界観にかぶれていたこともあって、ダークファンタジーの長編を書きました。架空の世界、大陸を舞台にした、剣あり魔法あり、国家間の戦争ありの構想だけはスペクタクルに富んだものでした。
この小説は、初稿は予選を通過したものの、二次予選を通過することができませんでした。しかし、のちに改稿したものが江戸川乱歩賞の最終手前まで残ることになります。最終に残らなかった理由は、「ミステリー要素が少ない」というものでした。そりゃそうです。ミステリーとして書いてないのですから。それでもそこまで行ったという方が驚きです。
その後は、国際政治や国際謀略戦をモチーフにした冒険小説をいくつか書きました。いま国際霊柩送還士を描いた「エンジェルフライト」という米倉涼子主演のドラマがありますが、まさにその国際霊柩送還士が国家間の謀略や紛争に巻き込まれるといった筋立てのものでした。これらはもうどの新人賞に送ったか記憶にありませんが、二次予選から三次予選まで行ったと記憶しています。
そのほか、ミステリータッチの探偵ものや、ファンタジー系の時代小説などいくつか書きました。いずれも20万文字を越える長編でした。このあいだ、小説講座にも参加していました。短い間でしたが、そこで得た学びは大きかったです。基本的な小説の書き方や執筆の心構えはこの講座で学びました。
その後、本業が忙しくなって執筆をする時間どころか本を読む時間も取れなくなってから、10年近く経ちます。この3年くらい、また小説を書きたいなと思いつつ、忙しさに紛れて、あるいは忙しさのせいにして、冒頭の「書けない、書くことがない、読むことすらできない」というループに落ち込んでいました。
そんなわたしにちょっとした転機が訪れました。まず、読むことについては、朝のジムでのウォーキングを機会に習慣が戻ってきたことです。いまは、外を散歩しているのでジムで読むことはありませんが、習慣が残っているので毎日必ず何ページか本を読むようになっています。梅雨が来たらまたジムに通うことになるので、さらに本を読む時間を取れるでしょう。
もうひとつは、AIとの出会いです。長編小説の執筆活動というのは、どんなに書くことが好きでも大変です。わたしにとっては、なにが一番大変だったかというと、孤独との闘いです。長編は構想時点から考えると、最低でも1年。長ければ2年は校了までかかります。わたしは新人賞に応募していた時期は1年に3作書いていたこともありますが、これは仕事の合間に書いているとしては例外的だと思います。
そのあいだ、誰にも相談できず(小説講座の先生に相談はできますが、なかなか小説の中身についての相談は難しかったです)、孤独に黙々と書き続けなければなりません。ときどき、心が折れそうになります。同じ場所をぐるぐる堂々巡りをしてしまったり、書く手がぴたっと止まったまま、朝を迎えたこともあります。完成の見えない旅を、地図なしで歩くようなものです。
そんなときに、相談できるのがAIだったのです。何度か書きましたが、わたしはAIに原稿を書かせるようなことはしません。だって、一番好きなプロセスです。それをAIであれ、他人に明け渡すことはできません。そんなことをしたら、そもそもわたしにとって書いている意味がありません。
わたしがAIとやり取りをするのは、テーマやモチーフに対する深掘りであったり、登場人物のキャラクターの深掘りであったり、書いたものの校正のためです。テーマやモチーフは独りよがりになることが多いのですが、AIは客観的な視座や俯瞰した視点をわたしに提供してくれます。
また、キャラクターの深掘りはなかなか面白いです。AIにその登場人物を演じさせるのです。年齢、性別、性格、人生の履歴書、好きなこと、嫌いなこと、といった基本情報をAIに与えてその人格でわたしとやりとりしてもらいます。あぁ、このひとはこういう考え方をするのか、こういうときにこういう行動を取るのか、そういった自分の頭の中だけでは見落としがちな気付きを得られることが多いです。
校正はいうまでもないですね。誤字脱字、リズム、全体の構成についていろいろアドバイスをくれます。ただ、それ全てが正しいわけではありません。間違っていることもありますし、どう考えてもわたしの感覚を優先した方が良いことも多いです。ただ、確かに気付かなかった点を指摘してくれることも少なくなくて、あくまで口うるさい最初の読者とか、アルバイトの編集者くらいのつもりで接しています。腹落ちしないことを取り入れることは決してありません。
これらのAIとのやりとりが、わたしの執筆での孤独を和らげてくれました。また、年齢が進むにつれて、だいぶ記憶力も怪しくなってきましたが、AIとのやり取りのログ自体がわたしの外部記憶装置のようになっていて、あのときAIとこんな話をしたな、と検索することが多くなりました。もちろん、残して置いた方が良いやりとりはメモ帳に転記してあります。わたしにとってAIは、あるときは「編集者」であり、「秘書」であり、「外部記憶」であったり「キャラクター俳優」だったりするのです。
そうやって、今回なんとか4万文字程度の短編ですが、1作書き上げました。今回書いてみて思ったのは、いきなり長編を書くのは、もう体力的にも集中力的にも厳しいかな、ということです。短編だとちょうど良い長さでした。ですので、今後は、短編連作で長編を構成するようなものを書いていきたいなと思っています。書きたいネタやモチーフもありますので、あとは時間を見つけながら執筆を続けていきます。
この歳で新人賞を狙っても年齢で落とされるでしょうから、まずは書くことを続けていきたいと思います。それなりに満足いくものができたら、noteで公開していくかも知れません。そのときは、是非感想などお聞かせいただければ幸いです。どこかで、あなたの物語とわたしの物語がすれ違うことがあったなら、それはきっと幸運なことだと思います。
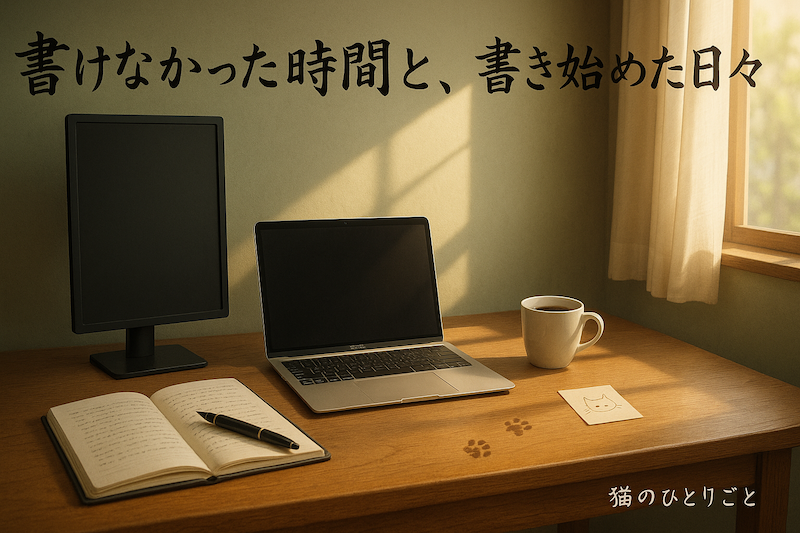

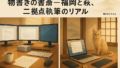
コメント