最近、食生活が少しおかしい。
昨日も一昨日も何を食べたか覚えていないことがある。特別なものを食べているわけでは無いのだが、自分が食事をしているシーンすら思い出せないことがあるのだ。
また、仕事の合間にほとんど無意識に甘いものを摂ってしまっている。食事が独立したイベントではなく、仕事をしながら、打合せをしながら、という「ながら」の中で行われる1つの作業のようになっている。
そこで、ふと気付いた。私はいったい何に興味を持っているのだろうと。
振り返ってみると、萩にいるときは何を食べたか覚えている。福岡に帰ってきて1週間以上経つが、いま何を食べたか言える。
とは言っても、別に贅沢なものを食べているわけでは無い。豆腐、納豆、ねじりちくわ、いわしバーグといった、ごくごく当たり前のものだ。しかし、毎日スーパーに通って自分で選んで買っていた。
一方で福岡にいるときは、食事の選択は相方任せだ。自分で買ったことも無いし、結果として何を食べたかあまり覚えていない。
何故、萩の方が食べたものを覚えているのだろうか。
それは、1人のときの方が自分の身体の声を聞けているからだ。自分で何を食べたいか選択しているからだ。
福岡では相方がいることで、その選択を放棄している。これは、相方の問題ではない。私の問題だ。
そういう意味では、仕事での30分刻みの打合せも、その合間に摂る食事も非常に象徴的だと言える。
もしかしたら、食への興味の喪失は、自分への興味の喪失なのではないかという気がしてきた。
「何を食べたいか」と自分に問うことは、「自分は何を求めているか」を問うことに他ならない。豆腐を手に取るその瞬間、私は自分の身体の声を聞いていた。自分が何を必要としているかを感じ取っていた。
それを放棄するということは、自分自身への関心を放棄することではないだろうか。
そして、自分への興味を失った人間が、他者に興味を持てるだろうか?
福岡にいるときは、言葉にし難い、姿の見えない「恐怖感」というか「危機感」のようなものが常に私につきまとっている。これの正体が、この「喪失」にあるのではないか。
確かに福岡では仕事は忙しい。しかし、忙しさは原因ではなく、主体性を手放す言い訳だったのかも知れない。
ならばやるべきことは明らかだ。
些細なこと、つまり、「今日は何を食べたいか?」自分に問うことだ。そして、自分でスーパーに行って「選択」することだ。
忙しくてスーパーに行けないのなら、相方に「これが食べたい」と意志を伝えることだ。
そこから、自分を、世界を、取り戻していく。
あなたは、今日何を食べたいですか?
大げさな話ではない。スーパーで豆腐を手に取るような、そんな小さな選択から、私たちは自分を、世界を、取り戻していけるのかもしれない。
少なくとも私は、そこから始めてみようと思う。

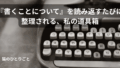
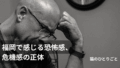
コメント