昨日は酷暑の中、萩博物館に行ってきました。萩博物館は山口県萩市堀内にある総合博物館で、2004年(平成16年)11月11日に「萩開府400年の記念日」として開館しました。この博物館の最も特徴的な点は、「萩まちじゅう博物館」の中核施設として、萩のまち全体を博物館としてとらえ、萩のおたからを保存・活用しようという新しいまちづくりの取り組みの一環であるということです。
建物自体も非常に魅力的で、萩市特有の武家屋敷風の広大な造りになっています。旧萩城三の丸にあたる堀内伝統的建造物群保存地区内にあることから、建物の配置や外観はかつてこの地区内にあった規模の大きい武家屋敷の特徴にならって設計されています。鉄筋コンクリート造でありながら、軒先には木材を、外壁には漆喰壁、なまこ壁、杉板下見張り壁などの伝統的素材を使用し、周辺の景観との調和を図っているのが印象的でした。
展示内容については、「萩学」と名付けられた萩の歴史・文化・産業・自然などに関する様々な資料を、観覧者が気軽に手を触れてみることができる体験型展示が特色です。特に高杉晋作資料室があり、幕末の志士たちの息づかいを感じられる展示もあります
高杉晋作資料室には当時の家族との手紙など実物が展示されていて興味深かったです。木戸孝允の晩年の頃の資料もありました。かつて木戸孝允は胃癌で亡くなったとされていましたが、いまは大腸癌が肝臓に転移したのではないかと言われています。その根拠となる当時の医者の所見の文書なども展示されていて、彼らが実在していて、わたしたちと同じように生活し、そして死んでいったのだなと思いを深くしました。
また、萩城があったころの城下町の地図やジオラマが展示されていて、現在の地図と比較をしてみました。自分の家が当時どこにあったのか、誰の家だったのか、史料として残っていて確認できるのは面白い体験でした。これも萩城下町という伝統地域に住むことができたからこそかなと思いました。いま、特別展示として夏季限定の「絶滅動物展-未来へつなぐ生きものがたり-」が行われていましたが、こちらは興味が無かったのでスルーしました。
これらの展示もさることながら、わたしの興味を惹いたのは、「萩ゆかりの人々」という通路の壁に貼ってあるパネルでした。政治・軍事、経済・産業、教育・文化、萩地域という分類に従って、歴史に名を残した人々の名前と何をした人なのか簡単なまとめが記載されています。これを一枚一枚読みながら、彼らが萩でどのように暮らしていたのか、その後の人生がどうだったのか、萩で生まれたことがその人生にどういう影響を与えたのか、ということに思いを馳せました。
幕末の志士たちも同様です。わたしにとって彼らは、あくまで「萩ゆかりの人々」の中の一人という認識です。そういう意味では、幕末のこの短期間に何故これだけの数の革命家と言っても良いような人たちが誕生したのか、萩という町がそれにどのような影響を与えたのかが気になっています。おそらく、萩という土地の特殊性、古くからの教育システム、地理的条件という3つの観点で考えることができると思います。
まず、萩という土地の特殊性が大きく関わっています。関ヶ原合戦で徳川家康に敗れ、大幅に領土を削られた上、交通の便のよくない萩に封じ込められた長州藩は、徳川幕府に対する複雑な思いを抱き続けている状況でした。これが長州藩特有の危機意識と反骨精神の土台となりました。
また、注目すべきは教育システムです。長州藩は、いち早く藩士の人材育成に力を注いだ藩のひとつで、その象徴が「藩校明倫館」。文武を尊ぶ「毛利吉元」が長州藩5代藩主となり、1719年(享保4年)に創設しました 。この明倫館は米沢藩の「興譲館」と並び、日本の学校教育史から見ても先駆けとなる存在でした。
さらに重要なのは、明倫館の出身である「吉田松陰」が幕末期に主宰した私塾「松下村塾」で、身分や階級にとらわれず塾生を受け入れたことで、多くの若者の心をとらえたことです。この教育の多層構造が、幅広い階層から革命家を生み出す土壌となったのでしょう。
地理的条件も重要です。長州藩領は三方が海に囲まれていたため、早くから官民共に、外敵に対する危機意識が強かったと思います。そういった地理的状況が、開国への対応を迫られた幕末期に、他藩よりも敏感で積極的な行動を促したと考えられるのではないでしょうか。
萩という町については、「人と土地との関連性」という観点からもっと深掘りしてみたいです。地元に残る史料を紐解いて、だれか特定の人物の一生を追ってみたいです。その人の人生を通して、萩という土地と人との関連性をわたしなりに解明していけたら良いなと思っています。できうるならば、小説という形で、それを残しておきたいです。

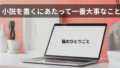
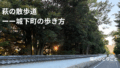
コメント