昨日は落ち込んだときに私を支えてくれる音楽について書いた。今日は、同様に落ち込んだときに私を救ってくれる本たちについて書こうと思う。
音楽同様、私は本も雑食で、様様なものを読む。ここでは、その中でも落ち込んだとき、危機に陥ったとき、何度も読み直している本を紹介したい。
まず、津本陽の『武人の階』。
以前も紹介したが、この本が私の文章のお手本だ。文字通り「座右の書」と言って良いくらい、何度も読み返している。創作に行き詰まったとき、気持ちが乱れたとき、この一冊を紐解いて、上杉謙信の人生に思いを馳せる。そうすると、心も落ち着き、精神が研ぎ澄まされたようになる。
次は、海音寺潮五郎の『孫子』。
特に「孫武の巻」は特筆に値する。他の孫子に関する本も何冊も読んだが、この一編を超えると思えるものには出会えていない。
孫武は占いや呪術に頼っていた戦争を、人間の努力と知恵の領域に引き戻した。その姿勢に、私は何度救われただろう。感情に流され、運命論に逃げ込みそうになる自分を、この本は合理的な思考へと連れ戻してくれる。
池波正太郎の『鬼平犯科帳』も挙げておかなければならない。
本当に落ち込んだときは、むしろ何も考えずにエンタテイメントの世界に入り込むことが良い場合もある。そういったときに読むのがこのシリーズだ。
平蔵にマネジメントとしての理想を見、人間の心は白黒にあらず、常に灰色のグラデーションであり、善悪などは相対的な観念でしかなく、1人の心のなかに同時に存在しうることを学んだ。
平蔵の年齢の設定は40代だ。いつの間にか平蔵の歳を越えてしまった。還暦を迎えてしまった今、また読み直したら何か新しい発見があるかも知れない。
創作論の本として、もうカバーも無くなり、本がボロボロになっているのは、ステーィヴン・キングの『書くことについて』という本だ。
これも創作の深い迷路に迷い込んだとき、その森の中から抜け出すために読む。この本を読むと、足元に矢印が見えるようだ。時々、さらに森の奥に誘うときも無いではないが、最終的には麓の街まで案内してくれる。
小説を書き始めたとき、この本の良さが全く分からなかった。と言うか、何をキングが言っているのか、さっぱり理解できなかったのだ。しかし、今なら分かる。彼の言う「道具箱」とは何を指すのか、何故ストーリーとプロットが別ものなのか、執筆という行為が何故化石の発掘に例えられるのか、今なら腹の底から実感できる。
翻訳物も挙げておこう。フレデリック・フォーサイスの『ジャッカルの日』と『オデッサ・ファイル』だ。
どちらも角川文庫の初版本を持っていたが、『ジャッカルの日』はボロボロになってページが四散してしまったので、平成25年の48版を買い直した。『オデッサ・ファイル』はまだ初版本を、蝶や花を扱うようにして読んでいる。
『ジャッカルの日』のスピード感と『オデッサ・ファイル』のどんでん返し。特に後者は、初読時の衝撃が今も鮮明に残っている。ただただ流れる涙を止めることが出来なかった。歴史の抗えないうねりの中で自分を貫く人間の姿が、私を励ましてくれるし、いつかこういう物語を書きたいと思わせてくれる。
落ち込んだり、精神的に辛い時期というのは、一様ではない。そのときの状況によって、読むに適した本は変わる。音楽のように聞く順番というものがあるわけではない。
ふと気付くと、読むべき本が目の前にあるのだ。私はその心の欲求に素直に応じることにしている。
今は、『書くことについて』を再読している。今回は仕事が忙しくて小説を書く時間が1週間ほど取れていないことが凹んでいる原因だと、昨日のエッセイで書いた。そう、私はまたありもしない暗い森の中に入り込んでしまって、途方に暮れて、座り込んでしまっていたのだ。
出口の灯りは見えている。私は無事、この週末に新作に着手することが出来た。
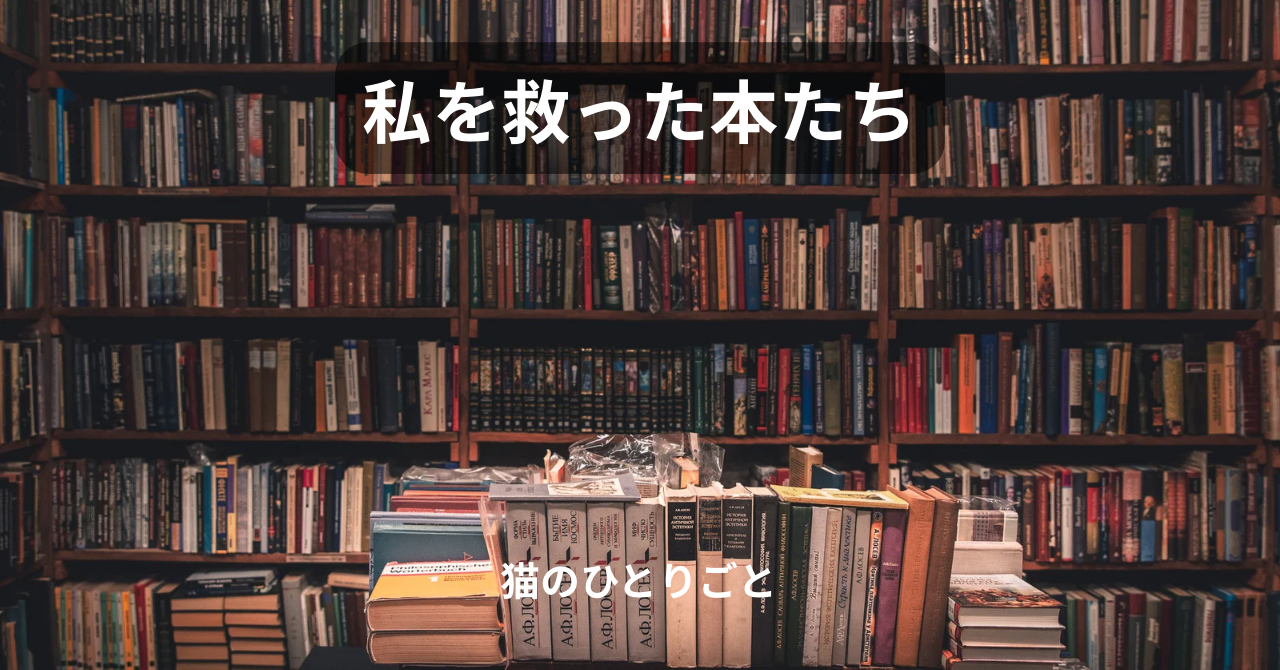
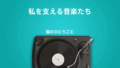
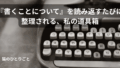
コメント