ここ数日、元気がなかった。原因は分かっている。小説を書いていないからだ。本業のIT仕事が忙しくて筆を取れていない。この週末になってようやく時間が取れそうなので、今日から新作に着手しようと考えているが、元気が出ないと筆も執れない。
こういう時、私は音楽を聴く。今朝も何曲か流していたら、だいぶ気分が戻ってきた。そこで今日は、私が落ち込んだ時に聴く音楽について書いてみようと思う。
トップバッターは映画音楽だ。「Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark」からエンディングテーマの「Washington Ending/Raiders March」。
言わずと知れたハリソン・フォード主役のインディ・ジョーンズのテーマ曲だ。
この映画を初めて観たのは大学生の時だ。その時の衝撃を今でも覚えている。中学生の時に「Star Wars」を観たときもそうだったが、今まで観たことの無い創作物を観たときの衝撃は、一生残る。その意味で、この音楽を聴くと、私は創作に関して初心に戻ることが出来るのだ。
次も映画音楽。「Flashdance」から「What a feeling」。
80年代、この手の音楽を主役にして(当時としては)現代的にアレンジした映画が流行った。「フットルース」や「サタデーナイトフィーバー」などなど。実は「トップガン」の1作目や「ロッキー4」なども、この範疇に入るのではないかと思っている。
これらの映画の楽曲は時代背景が今と比べると無邪気と言えるほど明るかったし、アメリカも元気だった。そういう時代のエキスを味わうことができる。
「Streets of Fire」という映画も上記の部類に入るだろう。ただ、この映画のすごいところは、あのウォルター・ヒルがB級映画を撮った、という点にある。低予算映画であるにもかかわらず、その雰囲気やスピード感、何とも言えない哀愁が大作に「見えて」しまうという作品だ。ダイアン・レインの出世作でもあった。
この映画中で使われた「Nowhere Fast」と「Tonight Is What Means to Be Young」を聴くと、当時のウォルター・ヒルがどのような気持ちで映画を撮ったのか、それまで不遇だったダイアン・レインがどうチャンスを掴んだのか、そういったことに思いを馳せることができる。そうすることで、私は元気をもらうのだ。
次はクラッシック。チャイコフスキーのバイオリンコンチェルトD Op.35。
チャイコのバイオリンコンチェルトは多くの奏者が弾いているが、Anne-Sophie Mutterとカラヤンの共演版が私にとっては最高だ。Anne-Sophieの清楚さと、カラヤンの重厚さが、あたかも少しいけない大人の関係を感じさせて、しかし後味の良い爽やかさも残す、名演だと思う。
カラヤンと言えば、ブラームスの交響曲第一番が良い。
この曲を聴いていると、暗闇の中で押し込められた希望や情熱が、後半になって一気に爆発するような感覚を味わえる。その曲調の変遷が元気をくれるのだ。
カラヤンの中で私が一番好きな盤だ。特に、1995年のベルリンフィルハーモニーのが至高。
最後は平井堅の「POP STAR」。突然日本の歌謡曲になり、かつかなり微妙なラインだが、この、「調子の悪いときに見る調子の良い夢」感は麻薬のようだ。癖になる。
この何とも不可思議な不合理感が、創作の本質を教えてくれるような気がする。実力のある歌手だからこそできる新しい試み。平井堅にとってもこの曲はチャレンジだったのではないだろうか。
他にも好きな楽曲はもちろんあって、気分によってジャンルもアーティストも変わる。新しい曲ももちろん聴く。
しかし、本当に落ち込んだ時は、初心に返ることができる曲、過去の自分を鼓舞してくれた曲、実力者になってもチャレンジを忘れないことを教えてくれる曲、そういった過去の曲たちが私を支えてくれるのだ。
今日紹介した音楽を頭からかけて、最後の「POP STAR」が始まった頃には、だいたいご機嫌になっている。
これらの音楽は、私の個人的な思い出に基づいているものでもあるので、汎用的とは言い難いと思うが、一度騙されたと思って聴いてみては如何だろうか。
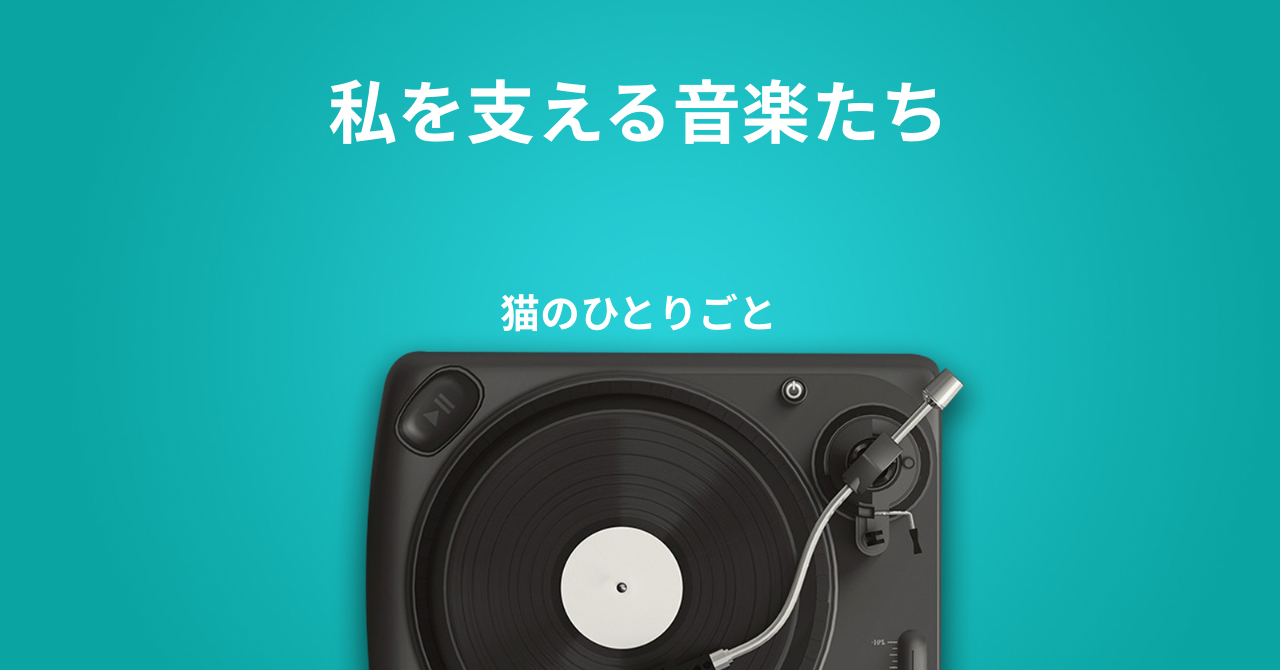

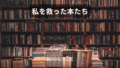
コメント