1か月ほど前から読み始めた司馬遼太郎『竜馬がゆく』。最終巻に入り、そろそろ終わりが見えてきました。いま、ちょうど大政奉還を竜馬が仕掛けたあとの、長崎における海援隊隊員による英国人襲撃事件についての話が進んでいるところです。
司馬史観と呼ばれる、幕末から明治への歴史の大転換を巡る解釈が正しいかどうかはおいておいて、毎日欠かさずこの本に接していると、竜馬という男を身近に感じざるを得ません。いままでどれだけの多くの人たちが彼に魅せられてきたでしょうか。
最後まで読み終えたらまた感想を書くつもりですが、今日は竜馬の死生観ともいえるものについてお話ししたいと思います。
わたしも若いうちは死というものの存在は遠くて、もちろんいつかは死ぬことは頭では分かっていますが、実感できるものではありませんでした。身内の死も小学生の時に父方の祖父が、大学に入って父方の祖母、社会人になって母方の祖父母が亡くなったときも、もちろん哀しかったですが、自分にとっての「死」へ紐付くものではありませんでした。
最近では、2年ほど前に愛猫が亡くなってしまって、非常に辛い思いをしました。そのときには、自分の年齢が50後半に差し掛かっていましたので、それなりに自分の死も意識するものでした。
でも、よく考えてみると、死というのは自分の人生の延長上に点として存在しているものではないのではないかという気がしています。社会人2年目か3年目のときに同期が亡くなったことがありました。顧客との接待の夜、寝ている間に吐瀉物を気管に詰まらせて朝には亡くなっていたのです。そのときも自分の死を意識できたかどうかは記憶が定かではありません。
しかし、彼の例でも分かるとおり、死というのは突然訪れるものです。決して80年、90年先に待っているものではなく、明日、明後日自分に訪れるかも知れません。つまり、死とは人生という線の先にある点ではなく、その横に寄り添うもうひとつの線なのではないか、そんな気がするのです。その線と線がいつ接するか、誰にも分かりません。
そう考えると不安になってきます。正直わたしはやり残したことがあるわけではなく、なにか今の世の中に心残りがあるわけではないので、そのときがきたらそのときだ、というようななんとなくの覚悟はあるものの、それでも不安は感じます。
『竜馬がゆく』での竜馬は、この不安にひとつの答えを用意しています。何度か本篇に登場する考え方で、「人間、生死を考えるべきではない」ということです。
これは、単に死を恐れず生きていけ、ということではありません。死をコントロールすることは(少なくともいまは現代医学では)できません。竜馬はそれを「寿命は天にある」という言い方をします。「人間は、寿命を天にあずけっぱなしにして、仕事に熱中してゆくだけでいい」と。
わたしは無宗教ですし、思想的になにか奉ずるものがあるわけではありませんが、ひとは生まれてくること自体に意味があると思っています。生まれてくる以上はなんらかの役割を持って生まれてくると思っています。そして、その役割に貴賤や軽重はありません。わたしの役割も、ほかのひとから見たら些細な役割かも知れません。でも、それはわたしにとっては、あるいはわたしの知らない誰かにとってもしかして意味のあるものかも知れません。
ですので、わたしは、寿命とはその役割を果たしたときに訪れるもので、普通の人間はその役割が何か知ることはできません。だからこそ、死がいつ到来するのか分からないのです。そうだとすると、わたしたちのやるべきことは、どんな些細なことでも、ひとつひとつ丁寧に、あきらめず進めていくことしかありません。いまやっている、そのことがわたしの役割であるかもしれないからです。
そういう意味で、竜馬の言葉はわたしが普段考えていることと一致していました。死を考えても意味がない。目の前にある仕事に熱中すること。その仕事のなかに運良く(運悪く? 笑)自分が果たすべき役割が含まれていたら自分に死が訪れるのだと。
自分に死をもたらす「役割」がなにかは分かりませんが、どうせやらないといけないなら、いい加減にやっても死という結果が同じなのであれば、ひとつひとつのことをそれだと思って丁寧にやっていきたい、わたしはそう思います。
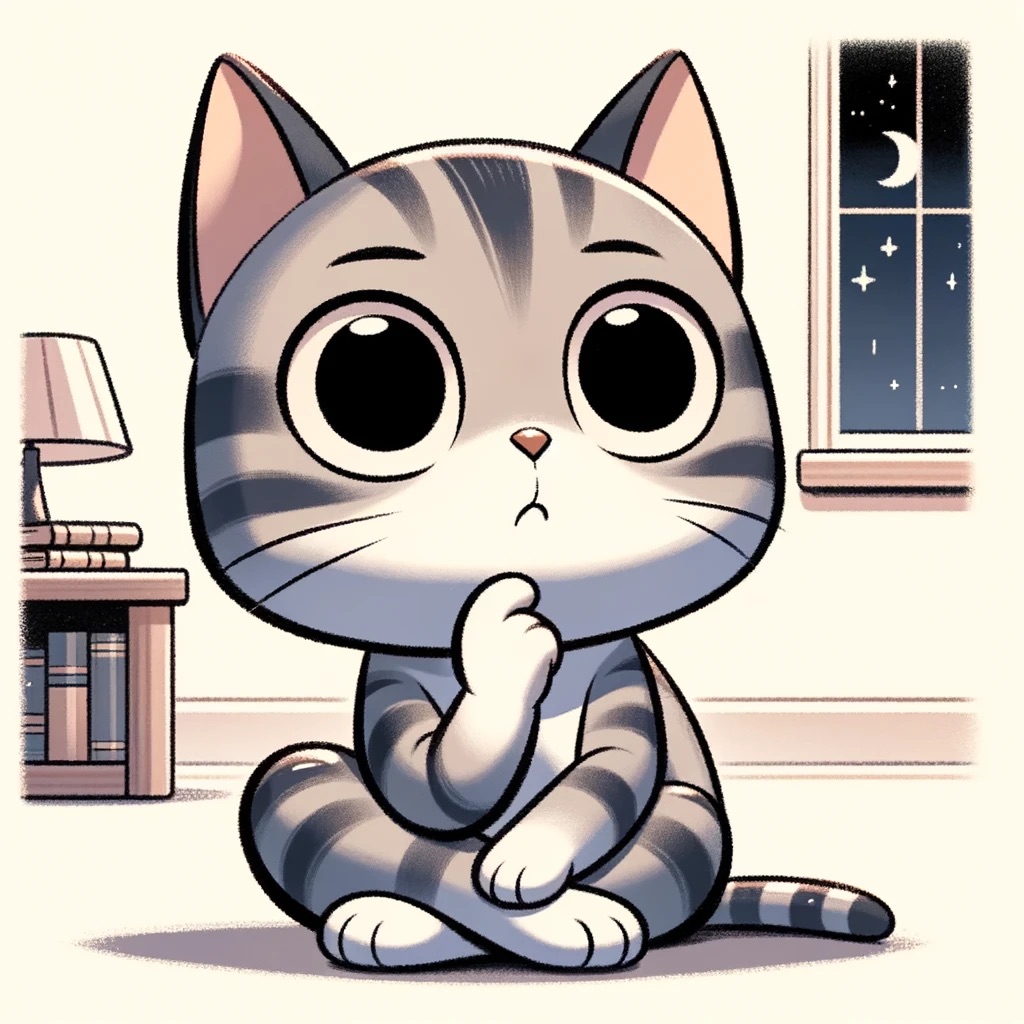


コメント