私は物を書くとき、AIを使っている。
AIを活用するためには、プロンプトを自然言語で適切に書くことが大事だが、精度を上げるためには、AIに与える情報も重要だ。
今日は私が物書きに最適だと考える、AIの執筆フレームワークについて書こうと思う。
AIはClaudeを使っている。日本語テキストの扱いに最も長けていると思うからだ。
資料集めや論文の整理など、扱うコンテキストが長いことが多いので、マックスプランにしている。
AIに渡す情報を蓄積する場所としては、Obsidianを使っている。
書き溜めた原稿やアイデア、AIとのやり取りのログは全てここに保存してある。AIはプロンプトに従い、あるいは自分の判断でここを参照し、書き込む。
物書きの観点では、もうひとつ大事なことがある。それはエディタだ。文章を書くツール。
私の場合は文章はAIに書かせず、自分で書く。そのため、特にエディタの選択には神経を使っている。
エディタは優れたものがたくさんあって、それだけで本が1冊書けるほどだ。ここでは、私が使っているエディタに絞る。
AIを物書きに活用するようになってから使っているエディタは2つだ。CursorとUlysses。
これらは、AIやObsidianとの相性で選んだ。
CursorはObsiduanとの連携に優れているだけでなく、AI自体を内蔵している(正確にいうと外部LLMを組み込んで使うことができる)。
文章を書いていて調べたいことがあれば、エディタ内部のチャットウィンドウを開いてAIとやり取りができる。
AIは複数のものから選ぶことができ、無料でも使えるし有料プランにしてコンテキスト量を増やすことも可能だ。
特筆すべきは、文章を書きながらAIが次に書くべき内容を推測して下書きしてくれることだ。
一方、Ulyssesはどうか。
Ulyssesはもともと独立したファイルシステム(テキストを管理するデータベース)を持っている。Markdown形式のファイルの機能は強力で、それだけでも十分長編小説を管理することができる。
しかし、小説の管理という観点でより優れていたのは、実はScrivenerだと思う。
ここで少し横道に逸れて、UlyssesとScrivenerについて書いておく。
Scrivenerは、原稿だけでなく登場人物や資料なども管理ができる独特のシステムを持っている。小説1本を1つのプロジェクトと想定して管理するので、文字数の目標や全体の構成の管理などに優れている。それと比べるとUlyssesは、小説と言う1つの塊を管理するには使いにくい部分があった。
ところがAIの登場が状況を変えた。情報を管理する保管庫としてObsidianが登場し、小説を管理するだけでなくAIとの親和性、連携が重要になった。
残念ながら、この点Scrivenerは対応できていない。一方UlyssesはObsidianとネイティブに連携することによって、その対応を果たした。
Ulyssesは既にあるObsidianの保管庫をそのまま使うことができる。デバイスにかかわらず、MacでもiPadでもiPhoneでも自動的に同期をしてくれる。
これはおそらくiCloudの機能だと思うが、シームレスに使えるためにあたかもUlyssesの機能であるかのように感じる。
話を戻そう。物を書くにあたって最も大切なことは、なんだろうか。
私は、思考の妨げをしないで文章を書き続けられることだと思う。私がCursorを物書き用途に使わない最も大きな理由はこれだ。CursorのメリットであるAIによる文章補完機能、下書き機能は、思考の邪魔になるのだ。
プログラムを書くにあたっては、この機能は非常に優秀である。
プログラミング言語は似たような文法やキーワードを繰り返し記述することが多い。そのため自分でタイピングするよりもAIにサポートしてもらった方が効率が良い。
しかし、日本語の文章を書く、物を書くと言う観点では、自分の頭の中にあった文章やコンテキストが、AIが支援することによって失われることがあるのだ。
平たく言うと、AIの書いた文章が目に入ってしまうと気が散る。自分の頭の中にあった文章を忘れてしまう。これは文章書くこと自体が目的で、それ自体を楽しいと思っている私にとっては致命的なことだ。
小説をAIに書かせようとする方にとっては、Cursorは良い選択肢になるのかもしれない。しかし書くこと自体が目的である私にとっては、CursorのAIサポートは残念ながら邪魔でしかなかった。
この点、Ulyssesはシンプルなユーザインターフェースと機能で思考や執筆の邪魔をしない。
もう一つ、Cursorを使わない理由は、内蔵されたAIではObsidianのコンテンツにアクセスできないことだ。
冒頭に述べたように、私の執筆活動はAIとの情報連携によって行われている。単にファクトチェックだけであれば問題ないのだが、蓄積されたテキストや情報に基づいて議論をしたり、アイディアを出したりすることができないと言う点は、致命的である。
- 小説ごとにObsidian保管庫にフォルダがある。
- フォルダの中には資料用のフォルダがある。ここには、Claudeがネットから集めた情報や、本・紙の資料をPDFにしたものをClaudeが整理したものを置いてある。
- 小説ごとのフォルダの下には登場人物の履歴書や年表、各種設定のファイルを置いている。
- 原稿フォルダの下に原稿を置き、Ulyssesで執筆している。
- 執筆にあたって行われたClaudeとのやり取りのログも、原稿フォルダと横並びのログフォルダに保存してある。
こうすることで、AIと適宜連携しながら執筆をすることができる。生産性は体感で倍以上、執筆時間も3割から4割は削減できていると思う。
いまの私にとっては、Claude、Obsidian、Ulyssesという組み合わせが、物書き用途では最適なソリューションと断言できる。
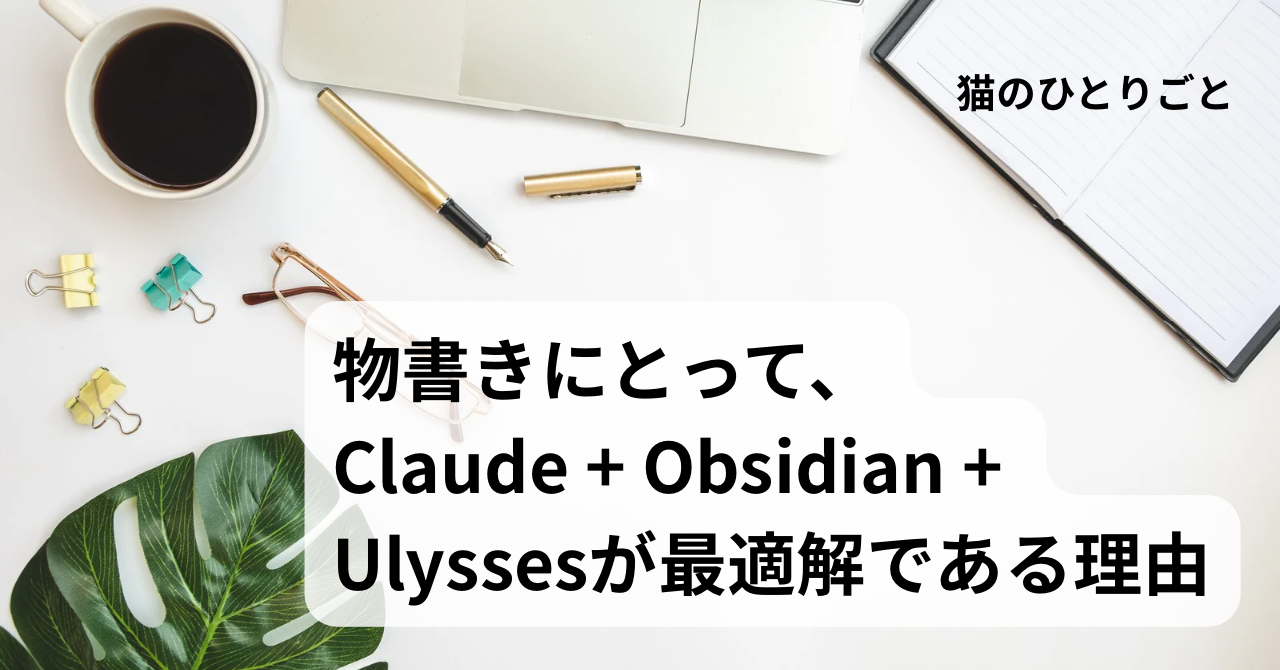
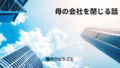

コメント