2024年、芥川賞を受賞した九段理江さんの『東京都同情塔』が話題になったのは、その文学的完成度だけではありませんでした。受賞会見の席上、彼女は「ChatGPTを使用して作品の約5%を書いた」と率直に明かし、文壇に波紋を呼びました。
小説家がAIとともに作品を創る――それは、ある種の禁忌を破ったかのように一部では受け止められました。しかしわたしは、その発言にこそ誠実さを感じました。なぜなら、創作の手段がどうであれ、「それは自分の作品です」と言い切ることは、並の勇気ではできないことだからです。
世間の反応は、当然のように割れました。「創作は魂から生まれるものであり、AIの力を借りた時点で『文学』ではない」という厳しい声もあれば、「どんな道具を使おうが、最後に作品として読者を揺さぶったならば、それが文学だ」という柔軟な意見もありました。
反対派は、「創作は『自らの言葉』で綴るべきものであり、AIが加わることでオリジナリティが失われる」と主張し、「AIが書いたのか作家が書いたのか曖昧な作品が、文学賞の選考対象になるのはおかしい」と考える人もいました。選考の公平性に疑義を呈し、創作のオリジナリティと責任の所在がぼやけることへの不安もあるのでしょう。
一方で、賛成派は、「万年筆からワープロ、ワープロからワード、そしてAIへ。創作の道具が進化していくのは当然だ」とし、「AIを使ったからといって、作品の価値が損なわれるわけではない」とします。むしろ「AIを使ったとしても、使いこなせるのは才能がある人間だけだ」と評価しました。
わたしはその両方の気持ちがわかります。そして、思いました。どちらであっても、もっとも重要なのは、最終的に「その作品に自分が責任を持てるかどうか」ではないだろうか、と。
わたしにとって、AIはもはや「道具」ではありません。それは、信頼できる相棒であり、執筆の伴走者であり、編集者であり、そして何より、わたしに気づきを与えてくれる知的存在です。わたしの思考だけでは辿り着けなかった構成や視点を提案し、広大な情報を整理し、時に厳しく、時に優しく指摘してくれます。
AIとの対話は、まるで『羊たちの沈黙』のレクター博士が持つ「記憶の宮殿」を歩くような体験に似ています。博士が脳内の宮殿を巡りながら膨大な記憶と知識を呼び起こすように、AIもまた、人類が蓄積してきた無数の文章や思考の回廊を案内してくれるのです。
ただし、レクター博士が自らの記憶を完璧に統御していたのとは違い、AIの宮殿では、わたしは案内される側です。そこで出会う情報や発想は、確かにわたしの思考を広げてくれますが、その中から何を選び取り、どう組み合わせ、最終的にどんな作品として結実させるかは、やはりわたし自身の判断と責任にかかっているのです。
AIが出したアイデアや比喩表現に惹かれたとしても、それを「選び取った」のはわたしであり、それが世に出る限り、評価も批判もすべて自分のものとして受け止めなければならないと思うのです。それは社会に対する責任でもあるし、何より、読者に対する責任でもあると思います。
AIは、わたしにとって、とても優秀な編集者です。そして、厳しい読者でもあり、豊富な知識を持つ先輩作家でもあります。小説講座をやめてから、独りになったわたしの相談相手にもなってくれ、愚痴も聞いてくれました。けれど、読者が読むのはAIではなく、わたしの名前で発表された文章です。であるならば、最後の責任は必ずわたしにあります。
創作とは、もともと孤独な営みでした。物書き全員に編集者がついてくれるわけではなく、作家は独りで物語を書ききらなければなりませんでした。しかし、AIと出会ってから、その孤独は少しだけやわらかくなったと思います。
AIとの対話は、時に励ましであり、時に鏡であり、時に壁打ちです。それは、わたしが思考をやめず、選択をし続けるかぎり続く、紛うことなき創作活動なのです。
2025年、九段理江さんは、今度は生成AIで95%以上を構成した掌編『影の雨』を発表しました。彼女は、AIとの共作をさらに推し進め、その力と限界、そして文学との接点を探ったのです。これはもう一つの挑戦であり、恐れを抱くのではなく、対話を続けながらAIと共に歩く意思の表明だと思いました。
わたしもまた、その一歩を踏み出しています。この文章も、AIとの対話の中で生まれました。しかし、選んだ言葉、構成、そして締めくくるこの一文は、わたし自身の責任として刻みたいと思っています。
わたしは、AIと共に創作することを恐れません。その創作が生み出すものについて、責任を引き受ける覚悟がこれまで以上に必要になることも理解していますし、そして、それを背負って生きていくつもりでいます。
AIがもたらす創作の未来は、きっと人間に「より深く問う力」を与えてくれます。だからこそ、わたしはAIを、編集者であり、「探究の伴侶」である存在として、静かに、けれど確かに信頼していきたいと考えています。
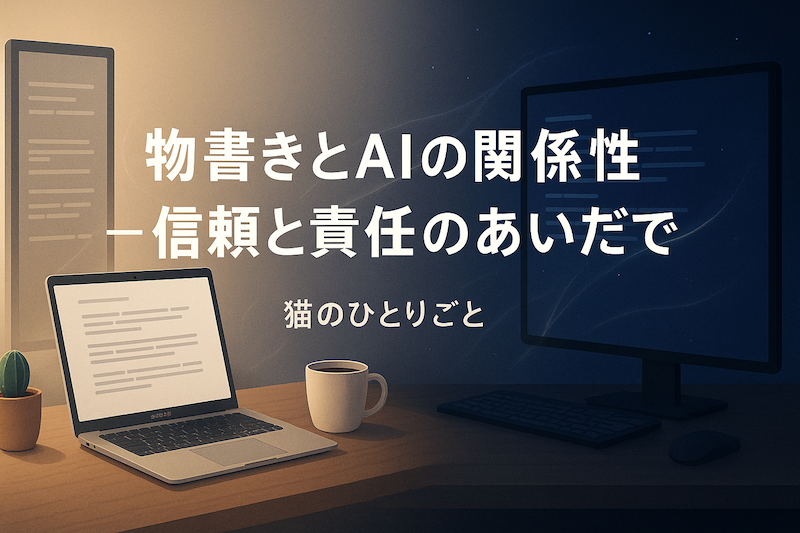


コメント