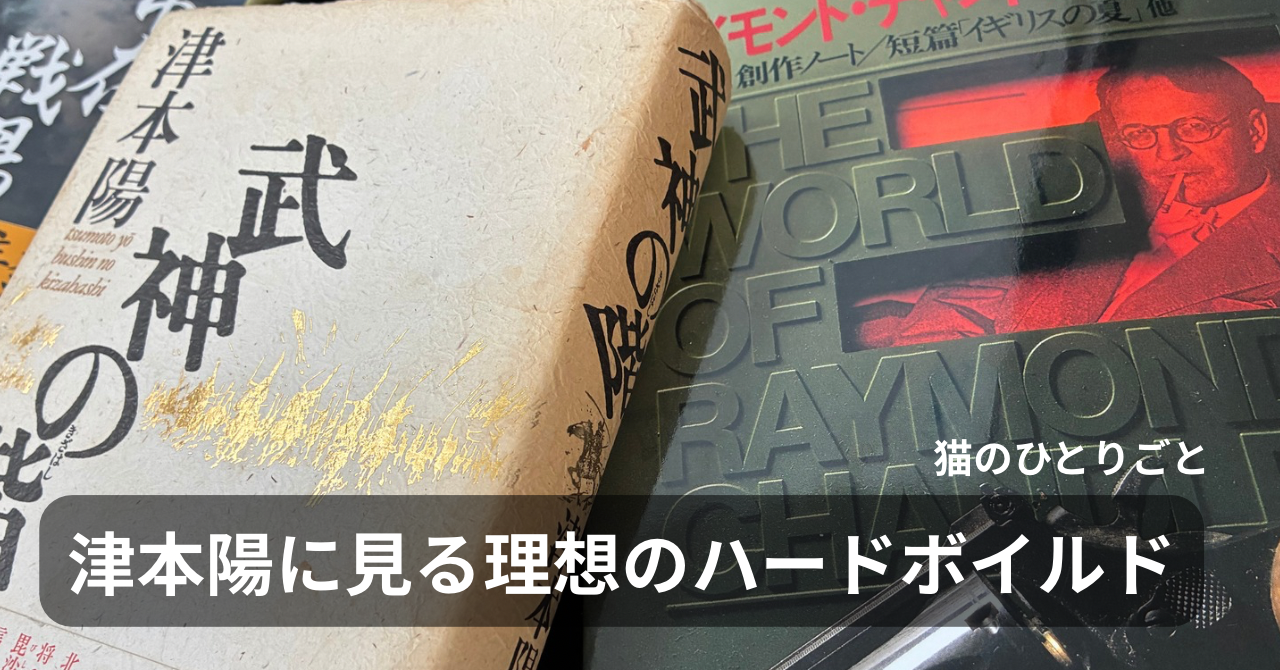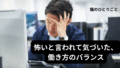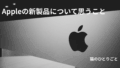私は昔からハードボイルドが好きだった。
大藪春彦の野性味、北方謙三の男らしさ、大沢在昌の緻密さ、そして矢作俊彦の実験性——それぞれに魅力があった。
もちろん海外の作家であれば、レイモンド・チャンドラー、ダーシル・ハメットなどの作品も愛読した。
ハードボイルドは作家や作品も多く、かなり掘り尽くされた分野と言えるだろう。なかなか新機軸を打つことが難しくなっていたが、2018年に大藪春彦新人賞が創設されてから、また新たな模索と試みが始まっている。
そんな中で、私も私なりのハードボイルドの姿を形にしたいと、ずっと考えてきた。いくつかの短編や長編を書いてみた。
しかし、どれもこれもどこかで読んだような、見たことのあるフレーズが並ぶ駄作だった。
煮詰まった私は、10年ほど前にいったんハードボイルドから離れて、様様な分野の小説を読み漁った。どこかに、何かヒントが無いか、テキストの森の中を彷徨った。
そこで出会ったのが、津本陽だった。
津本陽(1929-2018)は一般的に歴史小説家として知られている。『深重の海』で直木賞を受賞し、織田信長を主人公とした『下天は夢か』はミリオンセラーになった。
私は彼の作品を全て読んだ。そしてその中に、確かに「ハードボイルド的なもの」が潜んでいることを見つけた。
特筆すべきは彼の文体だ。津本陽の文章には、感情表現を意図的に排除した客観的記述、事実の積み重ねによる人物造形、そして現実と非現実を同列に扱う冷静さがある。これらは実は、チャンドラーが追求した「ハードボイルドの本質」と共通しているのではないかと感じたのだ。
私が好きな作品に『武人の階』という上杉謙信を扱ったものがある。
この中で、津本陽は「歴史的事実としての出来事と、作者の創作や解釈としての出来事——例えば死期間近の魑魅魍魎の出現——を同格に扱い、読者に判断を委ねる」という面白いアプローチをしている。
私はここには重要な技法が隠されていると感じた。
津本陽は超常現象すら「事実として淡々と記述」することで、かえって人物の心理状態を浮き彫りにしているのだ。これは感情を直接描写するよりもはるかに強烈な印象を読者に与える。
ハードボイルドという視点で彼の作品を読み直すと、以下の技法が見受けられた。
- 感情の「行動化」
- 目に見える行動で内面を表現
- 内面描写の「外見化」
- 心理状態を表情や身体の変化で表現
- 台詞に頼らない緊張感の創出
- 過去の「事実化」
- 感情的な回想を客観的事実に変換
- 具体的情報による人物造形
- 現実と非現実の「同格化」
- 技術的な詳細と人間ドラマを同じ温度で描写
- 読者の判断に委ねる部分を意図的に残す
これらの技法は、歴史小説だけでなく、現代日本が直面する新しい恐怖——AI、サイバー犯罪、見えないアルゴリズムの脅威——を描くのにも最適だ。なぜなら、これらの脅威は本質的に「目に見えない」「感情では理解できない」ものだからである。
私はこれを徹底して、「テクニカル・ハードボイルド」という新しい試みを続けていきたい。これは前にも書いたが、
- 暴力や性描写に依存しない緊張感の創出
- 純粋な日本語によるハードボイルド表現
- 現代的テーマ(AI、サイバー犯罪)との自然な融合
- 知的興奮による娯楽性の確保
を特徴とする新しいジャンルへのチャレンジだ。
津本陽が歴史小説において達成した「事実性と文学性の融合」は、現代ハードボイルドにおいても有効だ。彼の技法を学び、現代的なテーマと結びつけることで、私は翻訳調文体の呪縛や手垢の付いた比喩表現から解放され、私の理想の日本的なハードボイルドを書けるのではないかという実感がある。
それは同時に、暴力と性に頼らない新しい娯楽小説の可能性を示すことでもある。AIが我々の生活に深く浸透し、見えない脅威が日常を覆う現代において、津本陽的冷静さこそが最もハードボイルド的な武器となるのではないか。
津本陽が示した道を現代に延長することで、現代の「テクニカル・ハードボイルド」という名の、新しいジャンルの扉を開くことができるかも知れないと考えている。