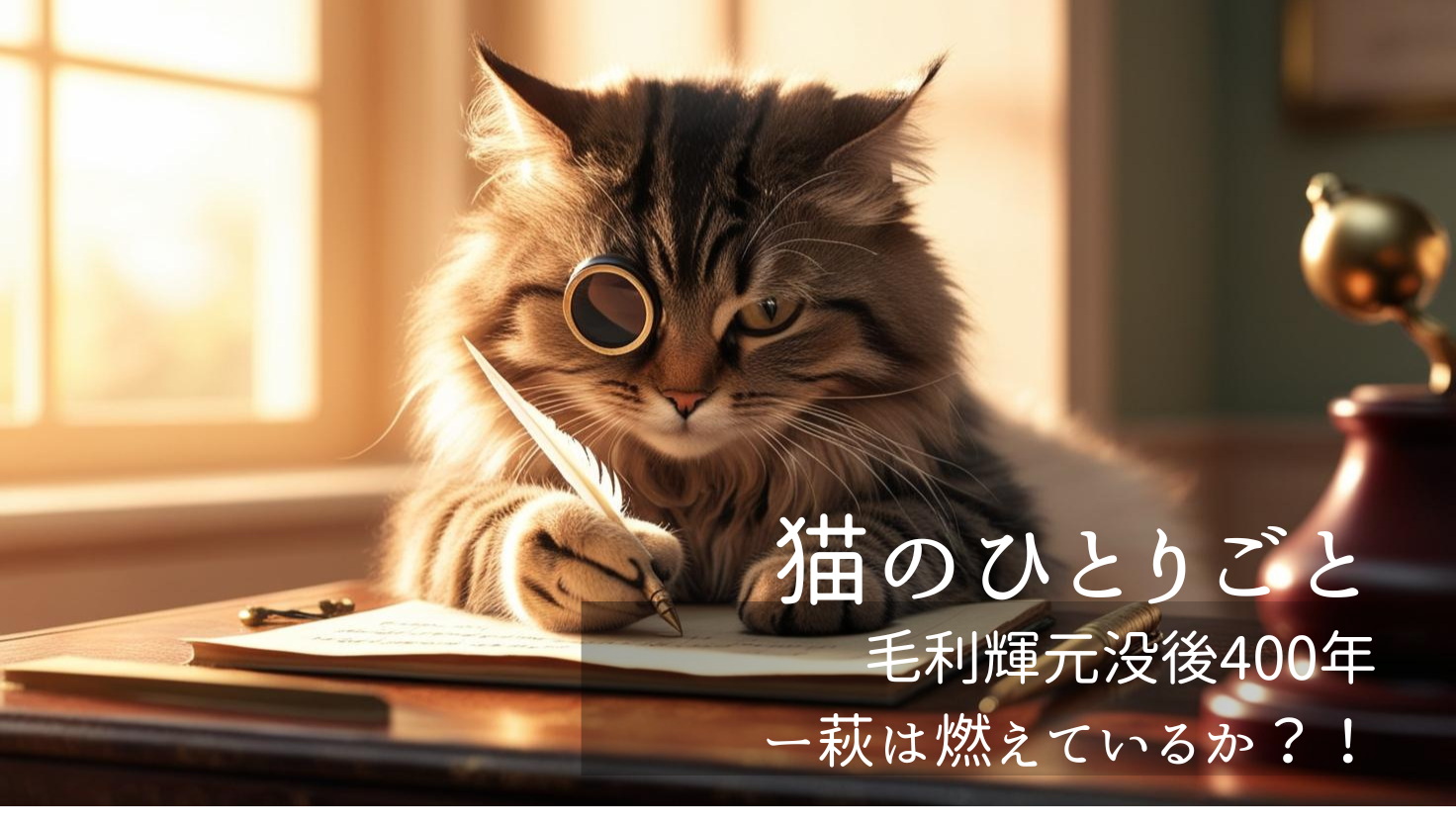昨日は、毛利輝元没後400年のお祭りがありました。例年であれば秋の「萩時代まつり」で行われる大名行列も、この4月27日にあわせて行われました。朝からさっそく、見物に行きました。
簡単に毛利輝元の紹介をしておきましょう。長州藩の開祖でもある輝元は、有名な毛利元就の孫に当たります。豊臣政権下では徳川家康や前田利家同様、五大老に座していました。しかし、天下分け目の関ヶ原の戦いで石田三成の呼びかけに応じたため、本戦には参戦しなかったものの、周防・長門2か国に減封されました。
萩城築城のあとは財政再建に努め、地域の産業振興にも力を入れました。そのため、他の大名よりは米への依存度が低い経済体制を敷くことができ、のちの幕末に、維新実現のための資金を投下できたといわれています。
治世は60年と長く、息子の秀就に家督を譲ったのが元和9年(1623年)9月、亡くなったのは、寛永2年(1625年)4月27日、享年73でした。
朝9時に天樹院墓所にて墓前供養祭、神事が行われ、次いで大名行列が始まりました。平安古備組(ひやこそなえぐみ)の行列が、「イサヨ~シ」の掛け声とともに次々に毛槍を投げ渡し、道具類の持ち手を交代しながら、城下町から萩城跡へ向けて練り歩くのです。
スタート地点は江戸末期の豪商菊屋家住宅前。そこから萩博物館、毛利輝元公銅像前を経て、萩城に入ります。この日、萩城跡指月公園では、さまざまな催しが行われていました。
わたしは、毛利輝元公銅像前で大名行列を見物しました。「草履舞」と「長州一本槍」も目の前で見ましたが、なんとiPhoneでの動画録画に失敗してしまいました。大名行列の写真だけここに載せておきます。

指月公園でのイベントは、昼まで参加しました。大名行列がステージの前に到着して終了したのが11時ころ。
そのあと、11時半から武芸の演武が始まりました。空手も剣道も合気道も全部やるという武道家が出てきて、型を披露しました。
ここでは、その型については、敢えて触れませんが、BGMの音楽はやめてほしかった。うるさいし、安っぽいし、かりに武芸が一流だったとしても台なしです。運営側の猛省を促したいです。
そのあと、12時から餅撒きがありました。山口では餅撒きが日常茶飯事に行われているとナレーションが言っていましたが、本当でしょうか。ナレーションいわく、山口では餅は買わない。餅撒きで1年分を手に入れるのだ、と。
それが嘘か本当かはわかりませんが、その後始まった餅撒きのすさまじさを見ると、あながちうそではないのかなという気がしました。
動画をこちらに載せておきますが、ここでもBGMがひどかったです。マツケンサンバが鳴り響いて、毛利輝元公もびっくりしたのじゃないでしょうか。
おかげで、YouTubeに動画をアップしたら、著作権に引っかかって動画を公開できませんでした。取り敢えず、音を削除しておきました。
無音の餅撒きもなかなかシュールですが、雰囲気だけでも味わっていただければと思います。