昨日は天気も良くて観光日和だったので近所にある松陰神社に行ってきました。近所と言っても、歩くと1時間かかるので、萩の町を周回しているまぁーるバスに乗りました。
まぁーるバスは西回りを「晋作くん」、東回りを「松陰先生」といい、東京の山手線のようにぐるぐる町をそれぞれ逆に巡回しているのです。目的地によっては遠回りになりますが、とくに時間に追われているわけではない、いまのわたしにとっては、街並みを楽しむつもりでのんびり松陰神社に向かいました。
いまさら吉田松陰を知らない方はいらっしゃらないとは思いますが、簡単にどういう人か書いておきますね。1830年、山口県萩に生まれた幕末の思想家・教育者で、明治維新の精神的指導者とされており、多くの志士を育てたことで知られています。
1859年、安政の大獄によって江戸で幕政批判の罪で処刑されています。享年29歳ですから、いまのわたしたちにとってみたらびっくりするくらい若いときに松下村塾を運営し、尊皇攘夷思想を提唱したわけです。
松陰神社は東京と萩の2カ所にあって、東京は墓所に、萩は実家の杉家に私祠が建立されたのが始まりです。萩の方は、1907年(明治40年)に伊藤博文らが中心となって県社の社格をもって松陰神社が創建されたとのことです。
神社ではありますが、境内に接するように松下村塾が現存しています。また、松陰が幽閉された旧宅も隣接していて、当時の生活が偲ばれます。
もちろん、神社にもお参りして、今後萩にも住むことを報告しましたが、個人的に興味があったのは、松下村塾として使われ、松陰が幽閉されていた杉家の方です。司馬遼太郎の本で読んでイメージしていたよりも、立派な家屋でした。
黒っぽい柱と、低い天井。襖を取り払うととても広く感じます。微かに匂う畳と、古い家独特の空気が、外は晴天であるにもかかわらず、屋内を薄暗く、冷たく湿った印象にさせます。

もともと杉家の一角にあった4畳半の質素な家屋で始まった松下村塾は、塾生たちが増えるにつれて、1858年(安政5年)、8畳を増築しました。有名な久坂玄瑞、高杉晋作たちも増築後に学んだようです。
その家屋の前でじっと耳を澄ませていると、塾生たちがどんな想いで松陰のことばを聞いていたのだろう、どういうことを考えていたのだろうと、自分もあたかもそこにいたかのような気持ちになりました。
松陰が幽閉されていた部屋は3畳。狭い部屋なのですが、何故かそう感じません。松陰はここで徹底的に本を読んだそうです。恐らく、彼の頭の中には広大な空間が拡がっており、そこに知識や情景や、ことばがところせましと格納されていたに違いありません。無限の3畳間、わたしにはそう感じられました。
松陰が松下村塾で塾生に教えていた期間は、ほんの1年とちょっとでした。それだけの短い間に、後の明治回天を実現する志士たちを育てたのだとしたら、とんでもない人です。
彼は当時の体制側から見たら、間違いなくテロリストの親玉です。もし、明治維新が成らなくて、幕府側が新体制を開いたとしたら、松陰の評価はそのようになっていたでしょう。いま、わたしたちが松陰を偉人として評価するのは、わたしたちの人生が、明治維新から繋がる歴史の上にあるからです。
当時はどちらに転ぶか分からなかったでしょう。それぞれの立場で力を尽くし、命を賭けた人たちは多かったと思います。その両方を、自分たちの歴史に繋がらない、別の歴史があったとしてきちんと評価することも大事なのかもしれません。
パラレルワールドという言葉があります。ある出来事や選択肢が異なる結果をもたらした場合に、別の歴史・文化・文明が展開される世界のことです。仮に、明治維新が失敗し、幕府が新体制を築いていた世界での吉田松陰の評価を考えてみました。
現実世界では、明治維新の精神的支柱として評価されてますが、この世界では幕府転覆を企てた危険思想家とされるでしょう。また、現実世界では教育者・学問の神として崇敬されていますが、この世界では過激主義者として軽蔑されるか、忘れ去られた人物となるでしょう。松下村塾も世界遺産ではなく、解体されて記録にしか残らなかった可能性もあります。
勝てば官軍とよく言われますが、結局のところ「歴史の勝者が誰か」によってものごとの評価は大きく変わるものです。わたしたちは今の世界、今の歴史の恩恵の中で生を受けた存在です。それはそれで大事にしていくべきですが、しかし別の世界線があり得て、そこで評価されるべき人たちがいたことも忘れてはならないのではないか、萩という歴史的な場所にいるからかもしれませんが、そんなことを考えてしまいました。
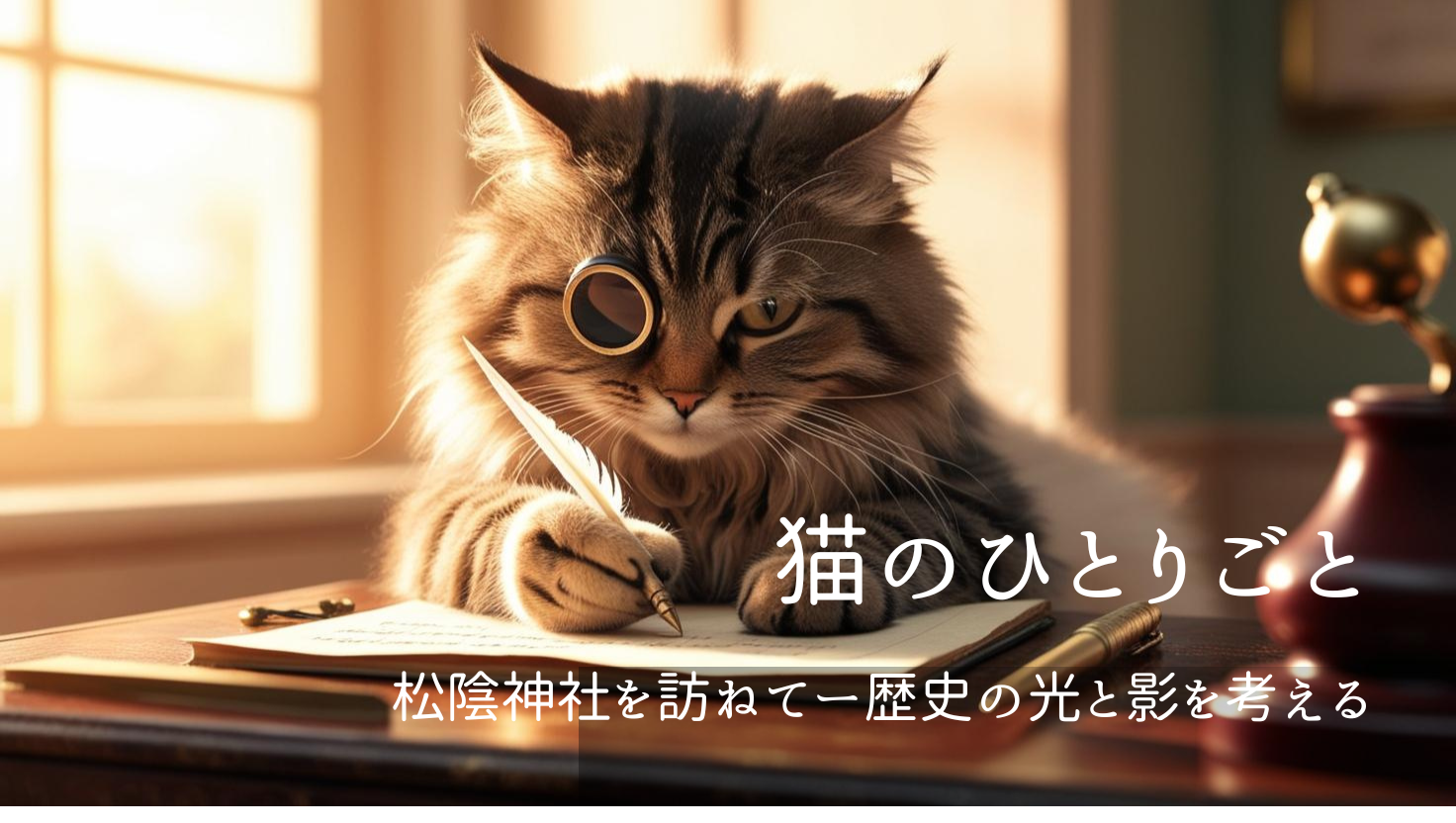


コメント