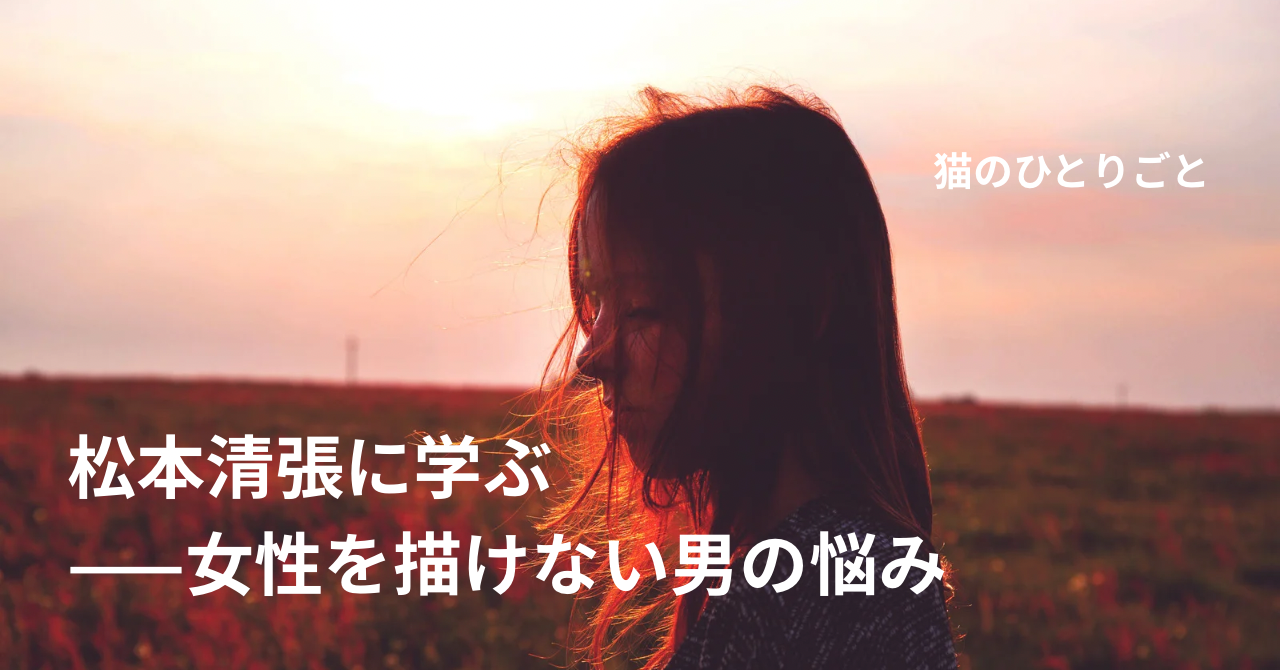GoogleかAmazonのレコメンドで、酒井順子という方の『松本清張の女たち』という本を読んだ。レコメンドを受けたとき、妙に昭和が懐かしくなってポチったのだ。
土曜日に届いて日曜には読み終わっていた。
内容は、昭和の社会派ミステリの重鎮、松本清張の作品を、特に女性がどう描かれているかという観点から分析し、昭和の女性たちが置かれた立場を詳らかにするものだった。従って、表現も今から見るとかなり際どい、ほぼアウトの言葉や状況が結構出てくる。
昭和って、とんでもない時代だったんだなと改めて感じた。
松本清張の作品はずいぶん昔になるが、有名なものはだいたい読んだと思う。『点と線』、『砂の器』などのいわゆる社会派ミステリのイメージが強く残っているが、結構人間関係、特に女性の暗部を描いた作品、例えば『霧の旗』、『黒革の手帖』など、ミステリと言うよりは世俗ドラマに近い内容も多い。
『松本清張の女たち』は、どちらかというと後者にフォーカスしている。
したがって、有名な作品を除くと、紹介されている作品のほとんどを私は読んでいなかった。個人的にも苦手な分野だ。読んだはずなのにすっかり題名を忘れているものもあった。
『天城越え』って松本清張だったのか、と今更ながら気付いたものもある。
この本を読んで思ったのは、何故松本清張はこんなに赤裸々に、女性の暗部と言っても良い心の内を描けるのだろうか、ということだ。
例えば、有名な『黒革の手帖』。主人公の原口元子は元銀行員。その彼女が銀行員時代に集めた情報を元に夜の街でのし上がっていく姿を描いている。元銀行員の女性が、どういう野望や欲望を持っているのか、上昇欲求は強いのに性的には淡泊で、そのギャップに苦しんでいるというようなことが、何故分かるのか。書けるのか。こういった私にはとても書けない作品が続々と紹介されている。
私は女性を描くのが苦手だ。と言うか、女性というものがよく分からない。女性が何を考えているのか、どういう行動を取るのか、好きなものは何で嫌いなものはなにか。よく分からないのだ。
例えば、昔ハードボイルド系冒険小説を書いたときのことだ。主人公の女工作員が敵国に潜入してバーで偶然ターゲットと遭遇する。主人公はターゲットと気付かずに惹かれて肉体関係まで持ってしまうのだが、これを読んだ相方が「これはない。こうは考えないし、こうはならない」と却下された。考えてみれば、そんな状況にある女心なんて、私に分かるわけがない。
私は異性愛者であることは間違いないのだが、どうも若いころから女性が苦手でまともに向き合ったことがない。深みに入ろうとするところで、スッと引いてしまう。松本清張の作品が描くところの、女性の心の奥底に踏み込むことを避けてしまう。
結果として、たぶん私は女性とは上っ面の関係しか結べていない。仄かな恋心で終わってしまう。
これは子供の頃の経験に根ざしているのかもしれない。
思い返せば、私は幼稚園の頃、幼馴染みの女の子を交通事故で亡くした。
まだ恋とか愛とか分からない時期のことだったが、その経験は私の精神の根元部分に刻み込まれて、消えてくれない。
この事実は、小説という人間を描く行為においては、本当にディスアドバンテージだと感じている。女性を描けないと言うことは、女性に読んでもらえないと言うことである。
平成18年の総務省の調査によると、「趣味としての読書」を行った人(10歳以上)の割合は41.9%で、70歳以上を除き、どの年齢層でも女性の方が割合が高くなっている。その他の調査を見ても読書人口全体では、女性の方がやや多い傾向にあり、女性はフィクション、男性はノンフィクションを好む傾向がある。
女性に読んでもらえないと言うことは、読書人口の半分を敵に回すに等しい。
『松本清張の女たち』によると、松本清張は必ずしも女性にもてたわけではないという。彼はどうやって女性を知ったのだろう。どうやってその心の動きを捉えて描くことが出来たのだろう。
『松本清張の女たち』にはそのヒントになるようなことが書いてある。
文藝春秋社で松本清張の担当編集者を長く務めた藤井康栄さんの言葉だ。彼女は、清張は編集者に対しても男女の差なく接していたと語る。「一人の人間として個人を見る視線を持っていた」と。
もしかしたら私は、必要以上に女性というものを特別視していたのかも知れない。女性を女性として捉えるのではなく、一人の人間として捉える。それが大事なことなのではないか。
私に足りないのは、女性に対する理解なのではなく、「人間」に対する理解なのではないか。
この本の語るところが松本清張の本質を突いているのだとしたら、私は日ごろの行いを改めなければならない。人間に興味を持つ。人間を男、女関係なく、一人の人間として捉えてしっかり対応する。観察する。そしてそれを書く。
そういったことを地道に積み重ねていけば、私にも女性が書けるようになるのではないか。今日、今この時から、それを意識して文章を書いていこうと思う。