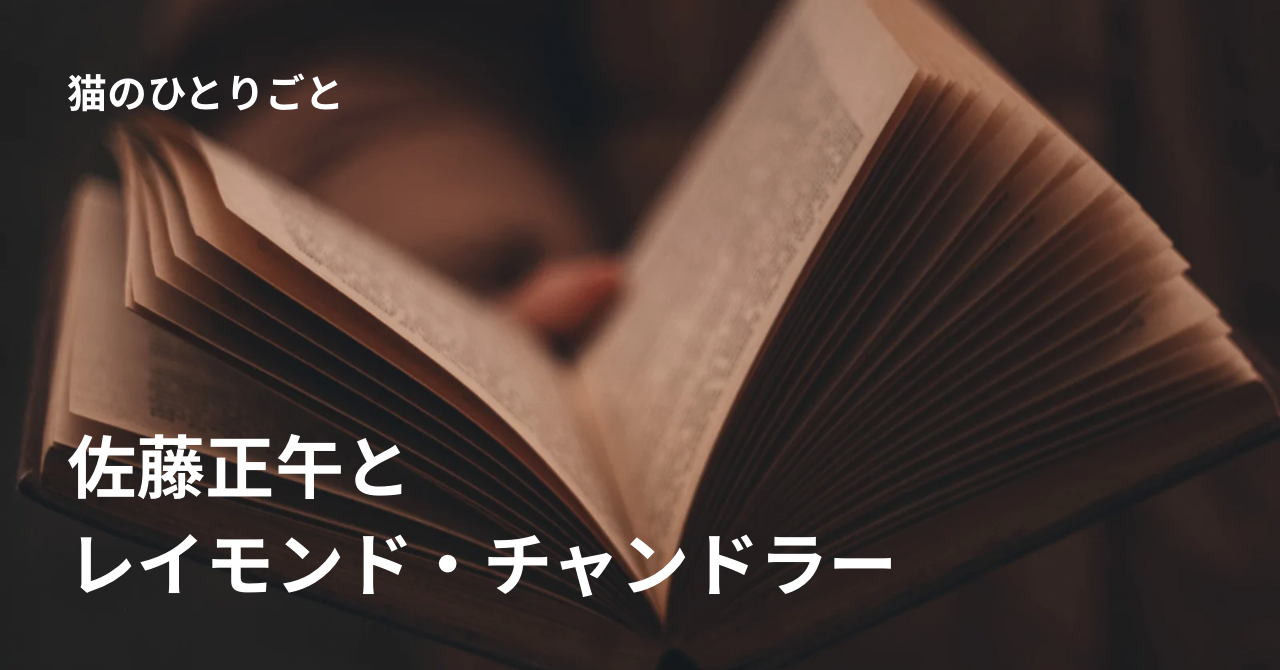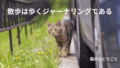私のペンネームは『佐藤正子(さとうしょうし)』だ。
変な名前、と思った方も多いと思う。プロフィールにも書いたが、私は小説家の佐藤正午を非常に尊敬しており、その文体に憧れている。
佐藤正午は1955年長崎生まれ。デビュー作は1987年の『永遠の1/2』で、時任三郎、大竹しのぶなどのキャスティングで映画にもなったので、ご存じの方も多いだろう。
現在は佐世保市で執筆をしておられ、「現代の志賀直哉」とも評される作家だ。
一見軽やかでユーモラスでありながら、深い哲学性と人間の心の機微を捉える繊細さを併せ持っている。特に会話文の自然さと、日常の中に潜む非日常性を描き出す手法は秀逸だ。
彼の作品は読者に「読み返したくなる」魅力がある。一度読んだだけでは気づかない細かな仕掛けや、何気ない描写の中に込められた意味の深さが、多層的な読書体験を提供している。
彼の最大の魅力は、個人的にはその文体にあると思っている。
独特の「色気と艶」がある。言葉の選び方、間の取り方、そして何より「言わないことで表現する」技術の巧みさ。冷たすぎず熱すぎない、ちょうど人肌のような温度感の言葉を選んでいる。
また、余韻を残す技術というべきか、文章を完結させすぎない。読者の想像力に委ねる部分を意図的に作ることで、読者が能動的に物語に参加するような構造になっている。
短文と長文のバランス、句読点の打ち方、改行のタイミングなど、文章のリズムが絶妙で、これが「艶」を生む大きな要素になっていると思うのだ。
一方で、恐らくその対極にあって、私が好きな作家にレイモンド・チャンドラーがいる。本を読む方でその名前を知らない方はおられないだろう。
チャンドラーの文体は佐藤正午と全く異なり、乾いた、削ぎ落とされた表現を使い、鋭い比喩、感情を排した客観的な描写、短文の連続によるスタッカート的リズムが特徴と言えるだろう。二人を対比してみるならば、
– 佐藤正午が「余韻」なら、チャンドラーは「切れ味」
– 佐藤正午が「湿度」なら、チャンドラーは「乾燥」
– 佐藤正午が「曲線」なら、チャンドラーは「直線」
と言えるかも知れない。
私の文体は、どちらかというと(巧拙は置いておくとして)チャンドラー寄りだと思っている。例えば、感情を直接描写せず行動や状況で示す傾向があるし、いわば観察者的な距離感がある。また、できるだけ余計な修飾を避けた簡潔な文章を心がけている。
ただ、技術的、論理的な文章を好むあまりに、行き過ぎると論文的、説明的な表現になるという課題もあるが。
これは、私の生き方自体に、できるだけ「客観的な視点」を持ちたい、「感情に流されない冷静さ」を保っていたい、という願望があるからだ。
私は佐藤正午のウェットな色気のあるテキストに憧れつつも、自分の向かう方向性は異なると思っている。
理想を言わせてもらえれば、従来のハードボイルドが持つ文体の魅力(簡潔性、客観性、緊張感)と思考の鋭さを保ちながら、暴力や性的要素に依存しない「クリーンなハードボイルド」の可能性を探っていきたい。
暴力や性的要素に頼らないエンタメの核は「知的な謎解き」、「心理的駆け引き」、「予想外の展開」だと思う。
難易度は非常に高いが、60年代のチャンドラーが都市の匿名性への不安を描いたのと同じように、IT化が進みAIが世界を変えていこうとしている今、現代人が抱えている漠然としたテクノロジーや将来への不安をテーマに描けたら良いなと考えている。