数日前、久し振りに台所でお湯を出そうとしたところ、鉄の錆びが大量に出てきました。しばらく放っておくと透明になりましたが、また数時間後に試すと同じように錆が出ます。浴室と洗面台でも試してみると、同じように錆が出ました。いずれも水の方は大丈夫です。
しばらくお湯を出し続けていると透明になりますし、飲み水に使うわけでもないので、そのままでも良いかなと思いました。しかし、毎回お湯が透明になるまで待つのも手間なので、業者の方に見ていただくことにしました。
最初は給湯器周りだということで、給湯器とガスを担当していたLPガス屋さんに連絡しました。この業者さんは、家の補修をお願いした建築会社さんに紹介してもらったところです。日曜でしたが、電話をしたところ、その日のうちに来て見てくれました。やはり、お湯側の配管が昔の鉄管のままで、それが錆びているようです。水の方はコーティングがされていて、錆びない状態になっていました。
翌日、そのお話しを建築会社さんにしたところ、即日水道屋さんを紹介してくれました。水道屋さんも、その日のうちに下見に来てくれました。そして、その日のうちに、見積が出てきて、2日後には実際に工事を行う手筈になったのです。
無茶苦茶展開が早くありませんか? わたしがガス屋さんに電話したのが日曜日の午前中でした。その3日後の水曜日の午前中には工事が完了したのです。いままで似たような経験は東京や福岡でやってきましたが、こんなに早く物事が動いたのは初めてでした。
普通に考えると、都会の方がシステマティックに物事が進められ、自動化されているプロセスも多いので、スピードが早いと思いがちです。しかし、今回の萩での動きは、それを上回るものでした。何故、都会よりも田舎の萩の方がスピードが早かったのでしょう。
ひとつは、人口の少なさはあると思います。その分工事の件数が少なく、業者さんの都合が付きやすい(言葉を換えれば暇である)状態にあるということです。ただ、Claudeに人口1万人あたりの水道工事業者数を推定してもらったところ、東京都は人口1万人あたり4.16社、福岡市は人口1万人あたり3.52社、萩市は人口1万人あたり2.46社ということで、むしろ萩の方が人口あたりの業者数は少ないのです。現代においては水道インフラの質が都会と地方で大きな差が無いとすれば、これが根本理由ではなさそうです。
もうひとつは、「紹介」の力です。「コネ」の力と言っても良いかも知れません。つまり、今回の場合、仲良くさせていただいていた建築会社さんの紹介で、ガス屋さん、水道工事屋さんを知ることができたということです。
地方では、独特のコミュニティが成立していることが多いです。出身校、出身地、血縁など様々なローカルな要素で人間関係が結びついています。そのコミュニティの力を借りることが、地方で生活するために非常に重要なのだと思います。
建築会社さんが知っている人が困っているとなると、繋がりのあるガス屋さん、水道工事屋さんにその情報がすぐに伝わります。知っている人(コネがある人)を知らない人(コネがない人)よりも優先して対応するという構図です。今回も、わたしが水道工事屋さんに話をしたときには、既にガス屋さんから(建築会社さんではありません)水道工事屋さんに話が伝わっていました。
これは、特に都会の方が地方に移住してきたときに非常に大事なポイントになります。わたしは、地方での生活を豊かに、スムーズにするためには、このコミュニティの一員に早くなることが重要だと考えています。そのためには、地域に入るときに最初に付き合う方を選ばなければなりません。できるだけ影響力のある、評判の良い方と接点を持つ、言葉を換えればコネを持つということが大事です。
わたしの場合、萩に第2拠点を作る際お世話になったのは、萩市が運営する移住定住支援組織「はぎポルト」でした。ここの支援員さんに紹介したもらったのが今回お世話になった建築会社さんでした。今でも覚えていますが、お薦めの建築会社さんを支援員さんやスタッフさんに伺ったところ、市内の業者さんのリストをいただくことができました。彼らの立場上、特定の業者さんを推薦するということはできないとのことでしたので、会社の規模や施工数などはわたしが調べて、最終的に業者さんを決めました。
現段階ではそれが、「当たり」だったということです。但し、これはわたしがその業者さんの「コミュニティ」に入ったことを意味します。そのコミュニティに属している間は快適に物事が進むでしょう。しかし、そのコミュニティのルールを破ったり、コミュニティ外の人や企業と関係性を作ろうとすると、その心地よさは恐らく逆に作用するでしょう。
地方に来て生活するのであれば、どの「コミュニティ」に属するのかを慎重に見極めなければなりません。新参者にはなかなかそれを判断することは難しいです。ひとつヒントになるものがあるとすると、やはり「地縁」でしょう。住む場所がどこか。その場所に住む方が属しているコミュニティに入ることです。わたしが選んだ建築会社さんも、わたしの住む地域で家を建て、地域の方が良く知っている業者さんでした。
「郷に入れては郷に従え」という言葉は歴史上様々に変遷しています。もともとは荘子に「入其俗従其令」という言葉があり、「あらゆる固定的価値観からの自由」を意味していました。中国の禅宗では「且道入鄉隨俗一句作麼生道」という言葉の通り、外的な順応が内的な解放につながるという逆説的な教えとして理解されました。日本にそれが入ってきて、鎌倉時代の教訓書である『童子教』では「入郷而従郷、入俗而随俗」となり、共同体の安定のための個人の努力を促すものに変化しました。現在ではそれが一般化されて、新しい環境に合わせること、組織の文化やルールを尊重することの意味になっています。
都会の人が移住するとき、それこそ「固定的価値観からの自由」を求めて地方に来ることが多いと思います。しかしそのためには、現実は地方コミュニティの文化やルールを尊重することを求められます。わたしはこの2つが相反するものだとは思いません。大事なことは、自分にとっての自由を確保するためには、自分にとって最適なコミュニティを選んでそこに入り、そのルールに従うことです。それができないのであれば、地方の方々にとってその人は破壊者でしかありません。そのことをよくよく認識しておかなければならないでしょう。
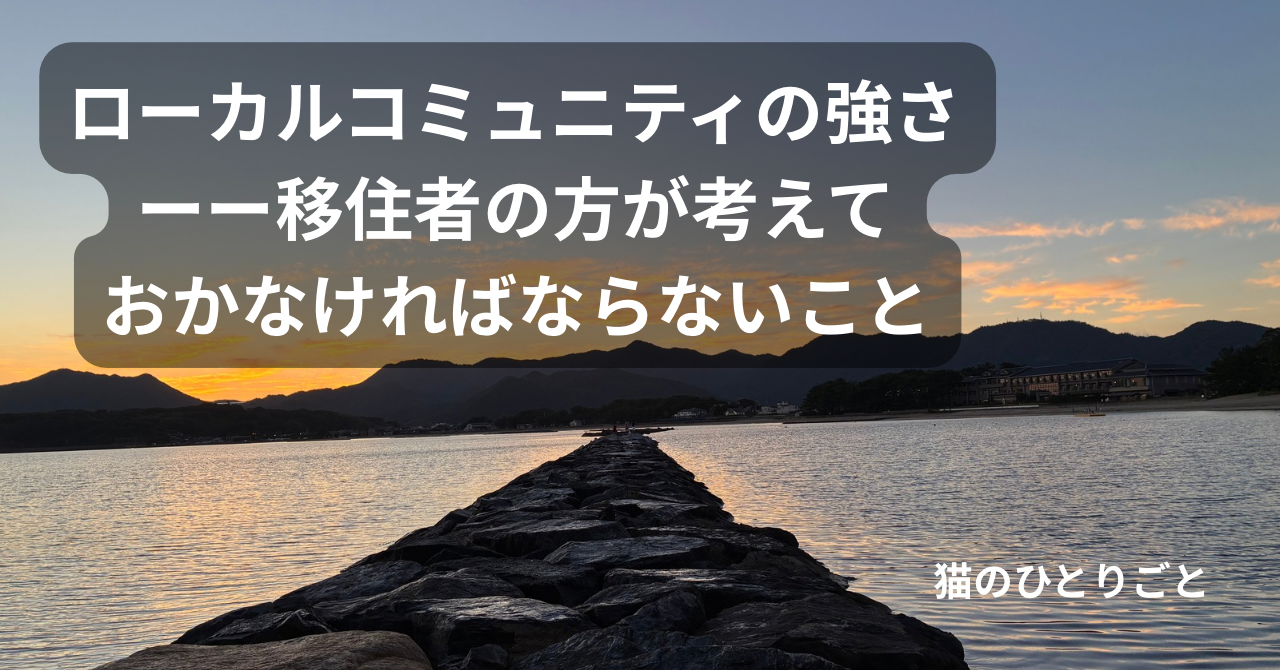
を観て思ったこと-120x68.png)

コメント