昨日、大分に日帰りで帰省しました。母の仕事を手伝うためでしたが、まるで役所に書類を提出するような、そんな感覚の往復でした。
福岡から大分までは特急で2時間強。東京から飛行機で帰っていた頃と、所要時間はそう変わりません。場所は近づいたはずなのに、気持ちはむしろ遠のいています。
ふるさとという言葉には、あたたかく、やわらかい響きがあります。帰りたい場所、戻りたい場所、心の居場所。かつてはそう思っていた時期もありました。夏休みに帰省するたびに、駅を降りた瞬間に感じた土の匂い、湿った風、少しなまった言葉。それらすべてが、心をほぐしてくれました。
実際、大学生の頃や新卒の頃のわたしは、大分に帰ると、出身の小学校や中学校の近辺を散歩することが好きでした。まだ、かろうじて、「あの頃の空気」が残っているような気がしていたからです。
けれど今の大分は、わたしにとって「帰りたい場所」ではなくなってしまいました。それは「帰らねばならない場所」であり、「用件をこなすための土地」になりつつあります。両親の老い、土地の変化、自分の心の位置——すべてが、少しずつ確実に、かつての「ふるさと」との関係性を変えてしまいました。
一方で不思議なことですが、最近第2の拠点として住み始めた萩という土地に足を運ぶとき、わたしの心はふっと緩むのです。もともと故郷ではありません。生まれ育った場所でもなく、家族の記憶が刻まれた土地でもありません。けれど、広い空と城下の白壁、海から運ばれてくる潮風、時が止まったような静けさには、今の自分が「還りたい」と思える何かがあります。
考えてみれば、「ふるさと」という言葉には、二つの意味があるのかもしれません。
ひとつは物理的なしがらみとしてのふるさと。生まれ育った家、年老いた親、相続の話や、使われなくなった部屋や食器棚。すでに自分のものではなくなりつつある場所との、「縁の調整」と言ってもよいでしょう。
もうひとつは、精神的な帰属としてのふるさとです。そこに行けば自分が「戻る」と感じられる場所。過去の想い出や、自分の輪郭を取り戻せる風景。それは必ずしも生まれ故郷である必要はないのです。むしろ、大人になった今こそ、自分で探し、自分で築くものなのかもしれません。
わたしにとって、大分は前者であり、萩は後者なのでしょう。どちらもわたしにとって必要な、大事なふるさとなのです。ただ、それぞれ役割が違います。前者はしがらみを解くために(あるいは維持するために)、後者は心を繋ぎ直すために、わたしにとって必要な場所なんだと思います。
ふるさとは、もしかすると、「自分の一部を置いてきた場所」なのかもしれません。大分には、記憶や感情を置いてきたのではなく、人間関係やコミュニティのなかで「まだ置かれている」自分の断片が残っています。
それに対して、萩には、過去に失くしたもの、しかしもう一度触れたいと思える精神の原風景が残っているのです。初恋の人が萩にいるわけではないのに、いまのわたしにとっては、大分よりも萩にいるように感じます。
たとえ実際にはそれが幻想であったとしても、そこに還りたいと思える心の動きがあるのなら、それは十分に「ふるさと」と呼べるのではないでしょうか。
ふるさとは一つではないのだと思います。そして、きっと、一つであるべきものでもないのだと思います。

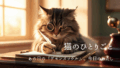
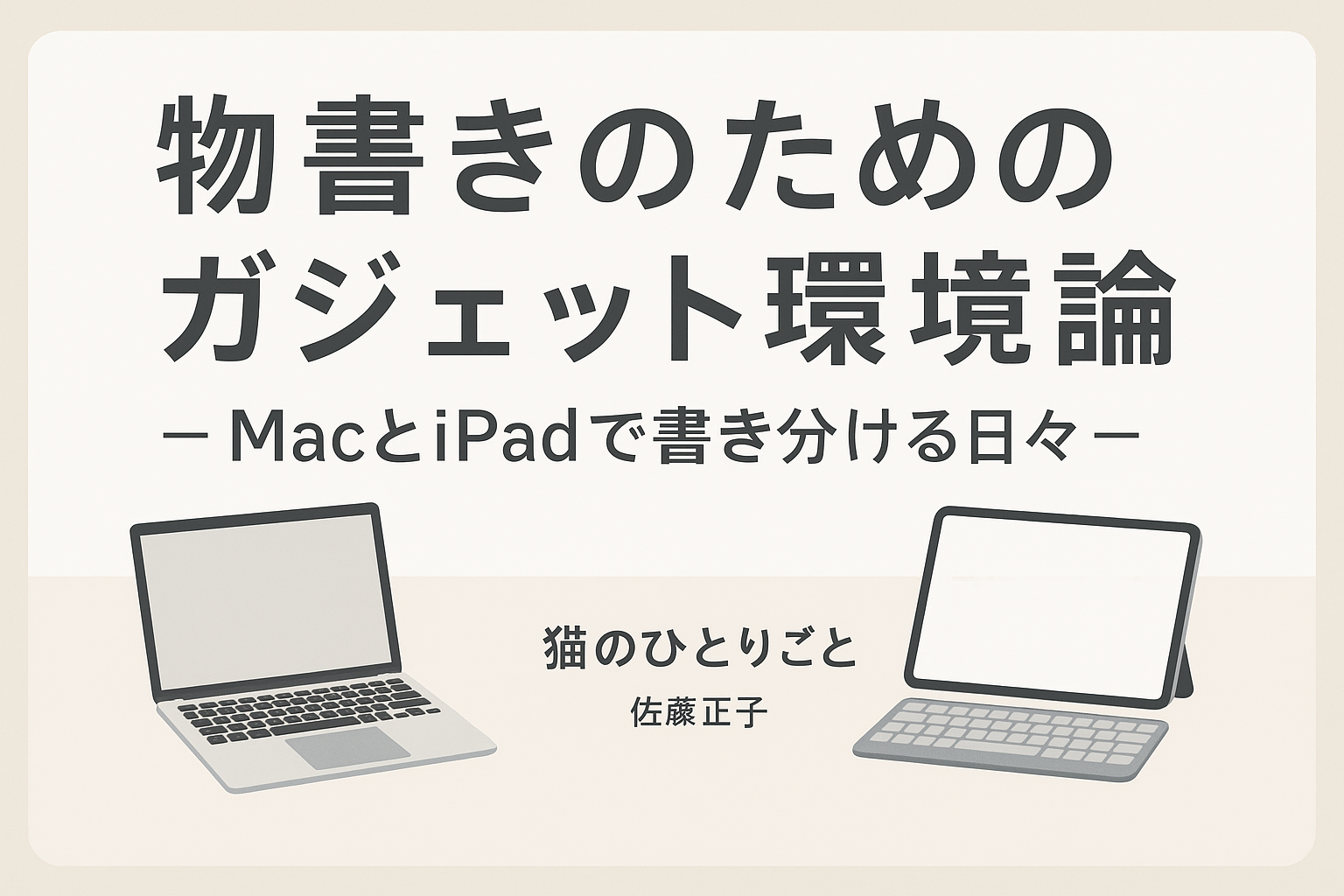
コメント