昨日は雲ひとつない晴天でした。とはいえ、まだ湿気はなく、爽やかな空気で、長袖のシャツを着ていても暑いとは感じません。
萩も海に面していますから、夏が近付くと湿気が増えてくるのだと思います。ゴールデンウィークは、梅雨の前のもっとも良い季節といえるのでしょう。
わたしも萩で暮らし始めたばかりですから、まだまだ萩のことは分かっていません。一年を通してみて、それぞれの季節を経験してみて、はじめてわかることも多いでしょう。いまは、春から夏の、この季節を存分に楽しもうと思います。
萩という町のプロファイルを簡単に紹介しておきましょう。
人口は4万人ちょっと。中国地方西部の山口県北部に位置し、日本海に面する市です。面積は700㎢弱あって、西に橋本川、東に松本川で囲まれた三角州で、北を上にして逆三角形の地形をしています。
海に面した北西には萩城跡があります。萩城は海に突き出た標高143mの指月山に築かれており、かつては「天然の要塞」と呼ばれていました。いまは、お城も鎮護のための寺社も廃されています。730mほどの登山道を上ると、だいたい20分で山頂に行けるようです。
萩城址の南には毛利家など武士たちの屋敷跡があります。碁盤目に整理された通りを白壁の建物が整然と並んで美しいです。
この城下の北側は海に面しており、菊ヶ浜という浜辺が広がっています。ここは夏は海水浴場になります。海岸線は美しい白浜で、沖に相島、大島といったちいさな島々があるためか、天気の穏やかな日は波が荒い印象はありません。荒い日本海というよりも、瀬戸内海のような内海の印象があります。
萩城北の総門を越えると、少し町の雰囲気が変わってきます。ここから東は商家が立ち並ぶ商人たちの町になります。道筋にはかつての豪商菊屋商人の邸宅や書院が残っており、当時の賑わいを想像させます。ちなみに、このエリアには高杉晋作や田中義一の誕生地、木戸孝允(桂小五郎)の旧宅があり、幕末維新が好きな方にはたまらない場所です。
萩中央公園の東には長州藩の藩校であった明倫館があり、その南には市役所などの役所が並んでおり、現代色が強くなります。バスセンターの近くにはショッピングモールやコンビニ、ユニクロなど多くの店舗があります。
個人的に嬉しかったのは、明屋書店があることです。大分にいた高校生のころ、大分の明屋書店にはお世話になりました。残念ながら大分の方は閉店してしまいましたが、萩の方はがっつり利用させていただきます。
あと、本といえばもうひとつ嬉しいことがあります。それは、明倫館の近くにある萩市萩図書館です。このゴールデンウィーク、時間を持て余したらここに篭もろうと思っています。
このように、萩という町は、こぢんまりとしながらもそれなりの規模を持ち、過去から現代にかけてのさまざまな史跡や施設、店舗がぎゅっと揃っています。ゆったりと町を散策する余裕がありながら、たいていのものは揃っていて便利、しかもほぼ歩いて移動できるいう、とても理想的な場所なのです。
地方の普通の田舎だと、自然は満喫できるけれど、不便だし、すぐに飽きてしまう。一方で、普通の地方の町は便利だけど、車がないと暮らしていけないし、微妙に寂れていて町が汚くなっているところが多いと思います。
萩は、その点、自然も歴史的な史跡も楽しめるけれど、同時に便利な場所でもあります。車がなくても歩けるし、自転車のレンタルや小さな巡回バスもあります。町自体が世界遺産に登録されているわけですから、美しく整備されています。
こんな場所、なかなかないとおもいます。同じ歴史的建造物に恵まれた場所でも、京都は都会過ぎます。金沢の加賀も良いのですが、少し広すぎるし、街並みが現代的すぎるかもしれません。中山道の馬籠、妻籠はもちろん良いのですが、少し遠くて、行くまでが大変です。
史跡がふんだんにあること、現代の生活を送るために便利であること。そしてちょうどよい広さと、福岡からの距離にあること。そういった理由から、わたしは、萩を最高に気に入っているのです。
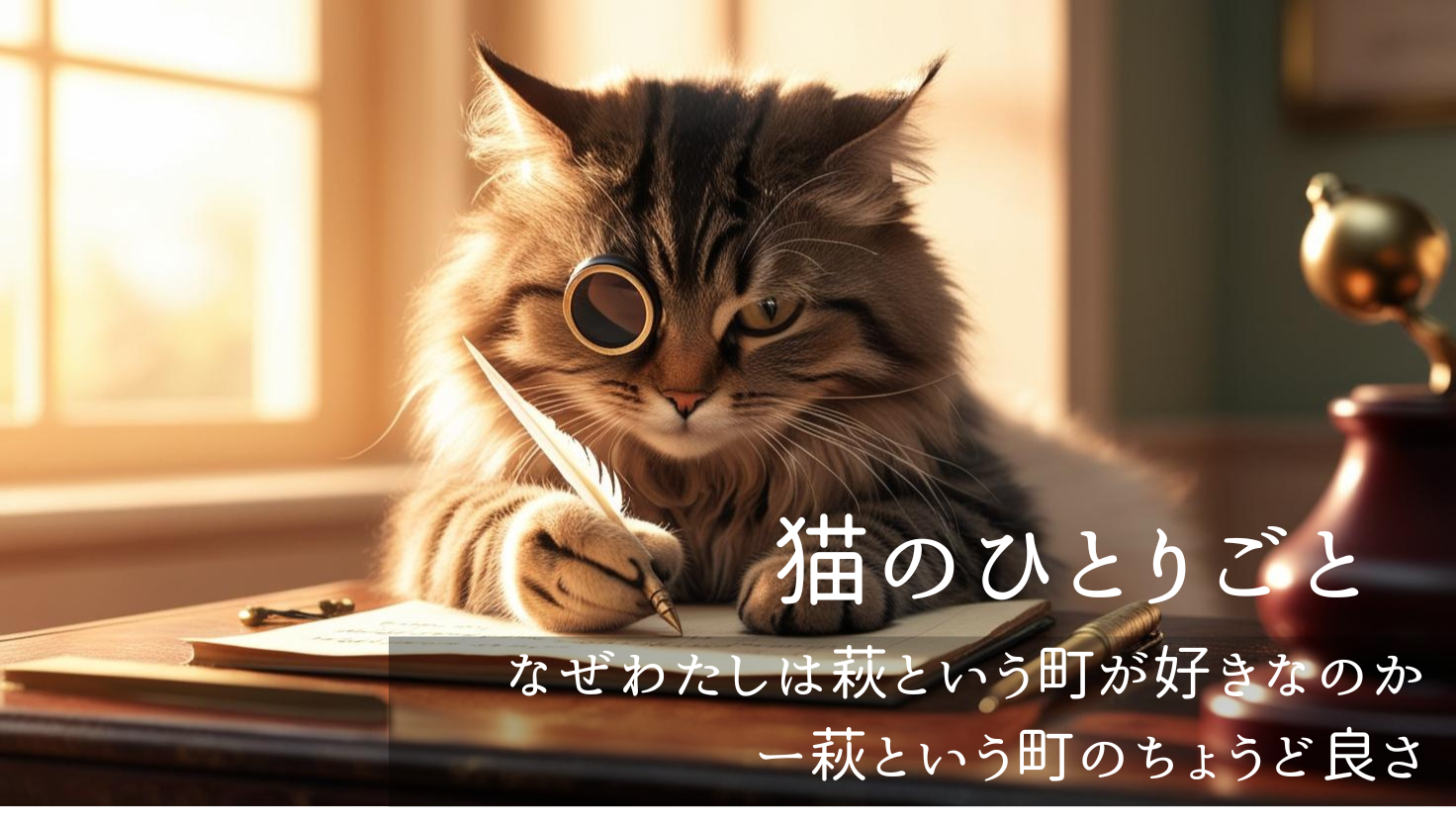


コメント